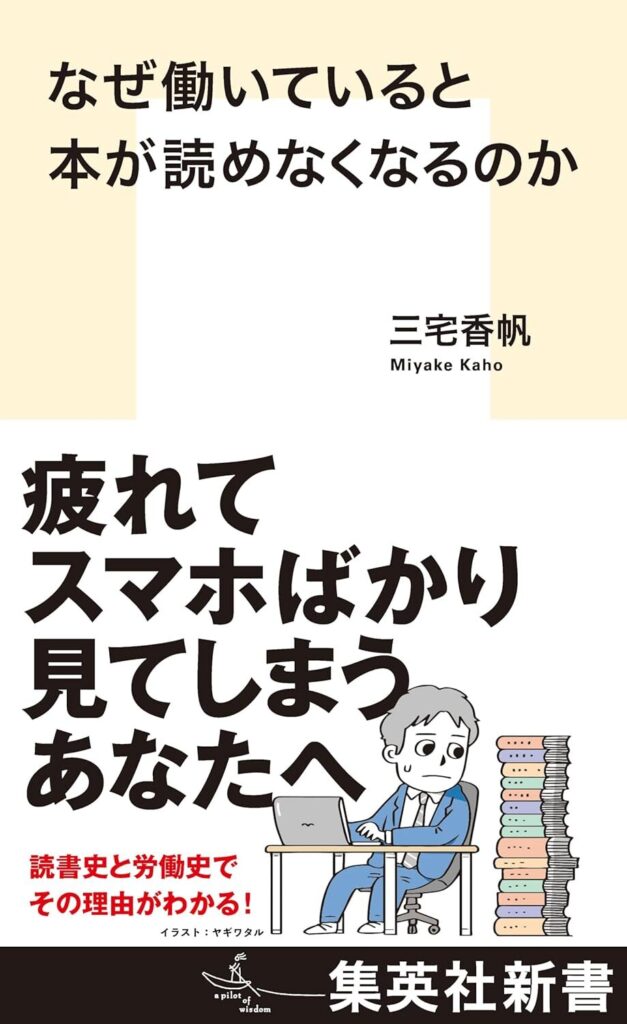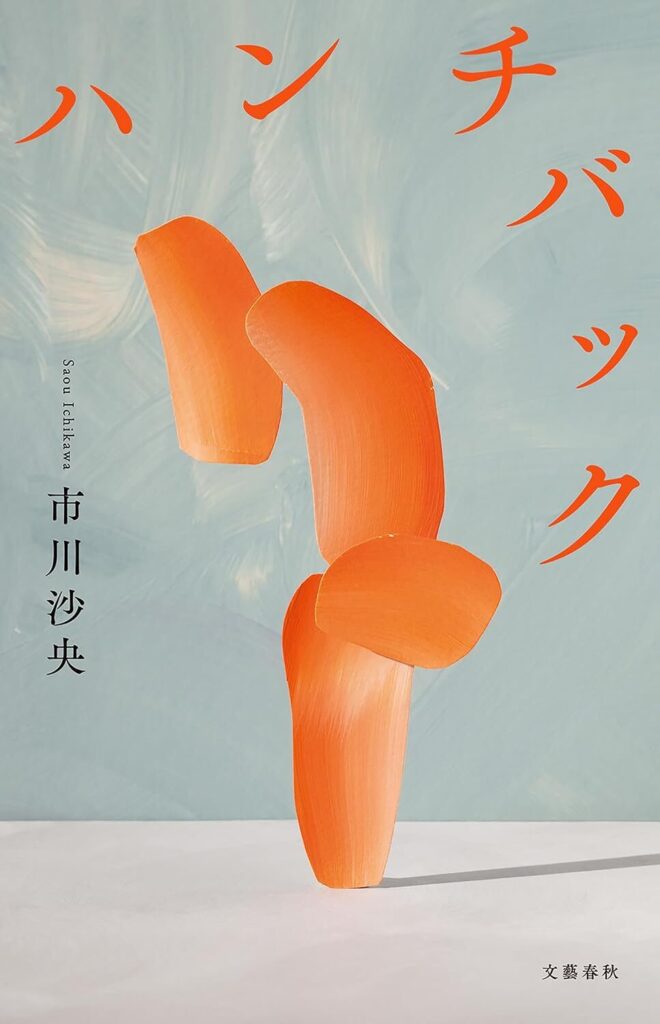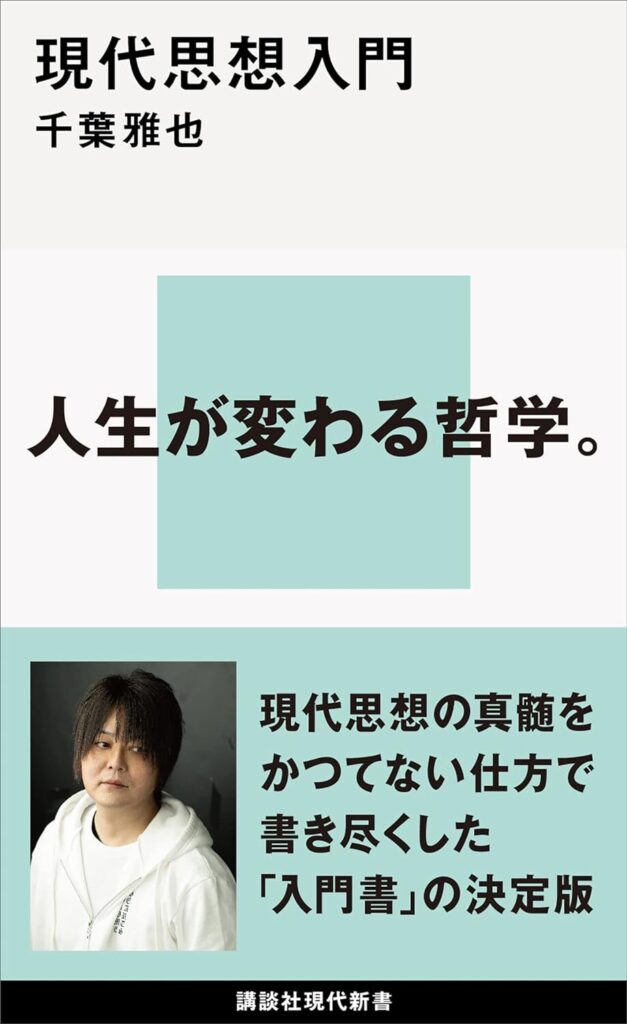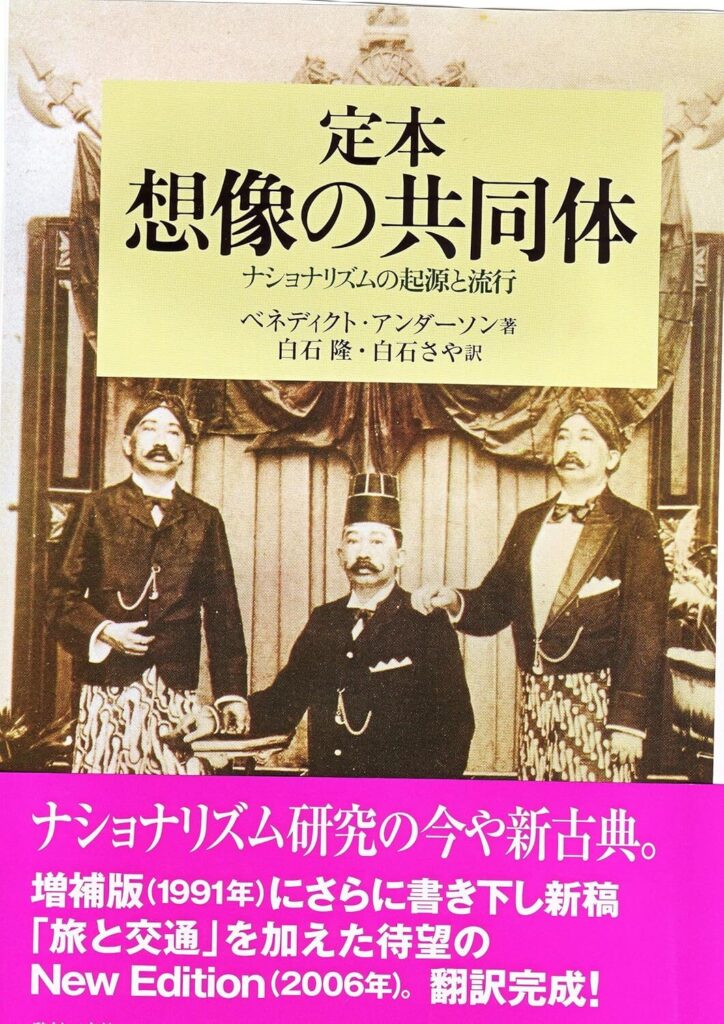※この記事には、三宅香帆「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」についての誤読があります。訂正箇所について本文中に記述があります。
ここに告白をする。
私は読書好きを名乗っているが、本を全て読み切っていないことが多い。
中途半端に読んだ本を、さも読み切りましたよと、したり顔で紹介している。
そしてここに告発しよう。
読書好きは全員一回は、読みかけの本をさも全部読みましたよ、というフリをして引用したことがあると。
「読みかけ本」
ところで世間では積読本、買ったけれど読まずに本棚に積まれている本が話題となっている。
たとえばValue Booksが運営する積読チャンネル、「積ん読の本」というインタビュー集が出ていたりする。
けれど私は、積読本というのはあまりにも大雑把なカテゴリーだと思っている。それは、買ったっきり一ページも読まずに放置している本と、途中まで読んだけれどやめてしまった本が含まれている点である。
私は、後者の、途中まで読んだけれどやめてしまった本を「読みかけ本」と呼びたい。
この記事で世間の知識人が本を読みかじって適当に話していることを糾弾するつもりはない。私もその一人だし、これからもしていくだろう。
私がこの記事で伝えたいのは、「読みかけ本」こそが現代の読書において最高で最強な存在であることだ。そして、読書人が公言していない技術であったりする。
これは本が読みきれない人間のポジショントークではない。
現代で働きながら本を読む唯一の方法が、「読みかけ本」をいかに増やしていくかである。
本は読み切ることが一番良いけれど、「読みかけ」でもちゃんと価値がある。
今回の記事では、まず最近の読書論を概観したのちに、実際に私が「読みかけ本」にしている3冊を挙げて「読みかけ本」の効能について考えてみる。
そして末尾には、私が今までの「読みかけ本」を記憶にある限り全て列挙しよう。それを見て、「こいつ、この本も読み切っていないのか」とほくそ笑んでくれても構わない。
読書論の外観
最近読書論について話題になることが多い。特に話題になるのが、
・三宅香帆「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」
・読書マッチョイズム
主にこの二点だろう。
雑誌の現代思想でも、2024年9月に「読むことの現在」という特集が組まれたように、読書についての関心は高まっている。
三宅香帆「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」
まず、三宅香帆の論点から整理しよう。
「なぜ働いていると本が読めなくなるか」は、日本における読書、自己啓発、独学の歴史を説明しながら、どうやったら私たちは働きながら本が読めるのかを紐解いていく。
この本の大きなワードは、「ノイズ」、「半身」だ。
「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」という問いに対する三宅の結論を言うなら、現代の多くの人にとって読書はあまりにも「ノイズ」が多いからだ。
「ノイズ」という言葉を言い換えるならば文脈のことで、読書は大きな文脈を読む作業となる。それよりはファスト教養的なコンテンツは文脈、「ノイズ」が少なく、楽に情報が摂取できる。
長い映画を見るよりは、文脈なんてないyoutubeショートを見ているほうが楽だろう。
そしてその解決方法は「半身」で労働すること。労働に自分の全てを投じるのではなく、半分ぐらいの労力をかけて労働する。そうすれば、読書する余裕が生まれる。
半身で労働するためには社会が変わる必要があると三宅は言う。週3勤務で、兼業の半身労働社会の成立によって私たちは読書をすることができるのだと。
もちろんそのように社会が変わってくれたら素晴らしいことだが、これは個人ベースでできることではない。現代で、恵まれた労働環境で働くことが可能な強者の論理感もある。
けれど、三宅の「半身」という表現は非常に重要だ。
※2025/04/20 訂正:三宅香帆「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」にて読書も半身で良いという記述がありました。筆者の見落としです。ここに謝罪します。
読書マッチョイズム
次に読書マッチョイズム論についてだ。これは、ネットだと元の議論がかなり歪曲して、読書マッチョイズム概念が広まっている節がある。
おそらく読んでいる人は、読書マッチョイズムといったら、本をたくさん読め的な教養主義的なマッチョイズムを指すと思っているだろう。例えば、岩波文庫100冊読めなどはその極みだろう。
けれど、読書マッチョイズムという概念は元々障害者における、読書の困難さがテーマだった。
読書マッチョイズムというワードは、市川沙央の芥川賞受賞作、「ハンチバック」に由来する。
「ハンチバック」には以下の文がある。
厚みが3、4センチはある本を両手で押さえて没頭する読書は、他のどんな行為よりも背骨に負荷をかける。私は紙の本を憎んでいた。目が見えること、本が持てること、ページがめくれること、読書姿勢が保てること、書店へ自由に買いに行けること、──5つの健常性を満たすことを要求する読書文化のマチズモを憎んでいた。
市川 沙央.「ハンチバック」 p 17
障害のない多くの人間にとって、本を取り、ひとまず文字を読むことは苦ではない。内容理解で苦しむことはあるかもしれないが、少なくとも肉体的な困難さは少ない。
けれど何らかの身体障害がある場合、100グラム程度の文庫本すら、持ち続けることに困難さを与える。大きなハードカバーなんてもってのほかだ。
その文脈で、読書バリアフリーという概念がある。身体障害、視覚障害などの人が本を読めるような環境づくりをしていくことだ。読書バリアフリーを達成するために技術的、制度的な施策が必要になる。
読書マッチョイズムは元はこのような意味が込められていた言葉だが、ネットではあくまで健常者内での教養主義に言い換えられてしまっている。
教養主義としての読書マッチョイズムが一人歩きするのはネット文化の一つだと思うが、せめて読書バリアフリーの文脈を知っていてほしいなと思う。
今回使うのは誤用としての教養主義的な読書マッチョイズムだ。市川氏の文脈を使わないのは申し訳ない。読書バリアフリーについて興味がある方は、現代思想2024年9月号「読むことの現在」を読んでみてほしい。そちらでは市川氏の対談や、識字障害の方の読書法が紹介されている。
教養主義的なマッチョイズムはいわば強者の論理だ。もう本が読めている人間に対して、本の読み方講座なんて何の役にも立たない。読書法を求めているのは本が読めない人たちだ。
いきなり岩波文庫を読め、という読書マッチョイズムはかなり無謀なものがあると思う。というのも、当たり前の話だが読書に慣れていない人がいきなり難しい本を読もうととしても、途中で意味がわからなくなってしまうし、疲れてしまう。
これは巷で言われる読書筋力の不足だろう。いきなり100キロのベンチプレスは持ち上げられないように、いきなり難しい本を手に取っても内容を理解することができない。
だからアンチ読書マッチョイズムの人たちは、入門者ルートを作って、こっちの優しい本から読みなとおすすめしていく。
これは、一番穏健な読書法な気がする。優しい本からレベルを上げていくように難しい本に挑戦してみる。
でも、少し過保護すぎるのではないだろうか。初心者には難しい本に挑戦するなというのは少し寂しすぎる。本を読むのに興味が出た人に対して、「その本難しいから、そっち読むよりこっちの本先に読んだほうがいいよ」と言うのはお節介なのではないか。
筋トレと違って、読書は負荷を間違えたとしても怪我をすることはない。いきなりニーチェを読んで、脳が破裂することなんてない。読書においての安全設計は考える必要はないのではないか。
「読みかけ本」という正義
読書論についての近年のトレンドに関しては概観した。
では、「読みかけ本」について戻っていこう。
「読みかけ本」の何が優れているか。
それは読書自体を「半身」にすることができるからである。本をいい加減に読み、本を読むハードルを下げていく。
三宅香帆は、働くことを「半身」にすることで、読書できるようになると主張した。
けれど私は、読書を「半身」にすることこそが、読書ができるようになる一歩だと思う。労働の環境は変えるのは難しいけれど、読書に対する態度はいくらでも変えられる。
本なんて、いくらでも読みかけにしていい。「読みかけ本」が増えていったって構わない。いい加減に本を読んでもいい。
本を読むとき、身構えて読む、何かを得ようとして読むのではなく、「半身」で読んでいく。読書は何も特別な行為ではない。
現代社会では、読書をすることが特権的、特異的になっている。その特異性を厄払いしていく必要がある。
そして、読書マッチョイズムにも、アンチ読書マッチョイズムにも私は反対する。
難しい本をたくさん読めばいいわけではないけれど、だからと言って初心者が難しい本に挑戦するのを止める必要もない。
初心者が難しい本を読んでいたら、口出しせず、「難しくて読めないや」と相談してきた時に、「こっちの本読めばわかりやすいよ」と言うのが正しい順番だ。難しい本をわざわざ取り上げる必要はない。
難しい本を読みかけにしたって構わない。それがむしろその人の実りになる。
では、これからは私の「読みかけ本」の実例を挙げながら、読みかけ本の良さについて紹介していこうと思う。
読みかけ本の告白
千葉雅也 「現代思想入門」 p140ぐらい
ドゥルーズ研究者で有名な千葉雅也の現代思想の入門的な本だ。この本は面白いから読んでとツイートした記憶もある。おそらく一番キャッチーに現代思想を学ぶための良い本だ。現代思想で一番有名なデリダ・ドゥルーズ・フーコーの紹介をしていき、その背景となったニーチェやマルクス、さらにはラカンなどに触れていきながら、最終的には、メイヤスーなども紹介していく入門書だ。
さて、ここまでの紹介だとさも読んだことあるように語っただろう。だが、私は読み切っていない。先に書いたが、140ページぐらいで読むのをやめてしまった。別に悪い本ではない。いい本だ。ドゥルーズ・デリダの思想の概略はこの本で知った。
だが、一度本棚に戻したあとに放置してしまっている。
読みかけ本になってしまうのは、何も内容の難しさで放り投げるだけが原因ではない。途中でその本への集中力が切れてしまい次の本を読み始めてしまったり、ふとしたタイミングで本棚に入れて忘れ去られた本も多いだろう。
私は、面白いなと思った本もなんだかんだ「読みかけ本」にしている。読むのが億劫なのが一番の原因だが、面白い「読みかけ本」が本棚に眠っているのは安心できるのかもしれない。本棚からその本を取り出せば、面白さが担保されているのだから。
ベネディクト・アンダーソン「定本 想像の共同体 ナショナリズムの起源と流行」p150ぐらい
「想像の共同体」はなぜ国家が生まれたのかという、大きなテーマを扱っている。そこでの主張は簡単に言えば、国家というものは存在しない、人々の想像の中だけに存在するものだと主張する。
ではどのようにして同じような想像を持つようになったのか、その大きな要因は出版だという。出版、つまり活版印刷が生まれる以前、人々の共通言語はラテン語で、ラテン語が読める知識層だけがヨーロッパという共通の意識を持っていた。けれど活版印刷が生まれ、簡単にコピーが出来るようになり俗語(普段話す言葉)での出版物が増加した。
その結果、俗語が固定されフランス語、ドイツ語などある規模の地域で共通の言語が生まれるようになった。
出版以外にも、教育によって共通語が教えられるようになったのも理由の一つだが、教育をするにも同じ教科書がないといけない。そのため出版が共通語を生み出した要因の一つだ。
言語が同じだったら同じ共同体という意識が生まれる。そして、国民というものが出版によって生み出されていった。
この著作の主張の骨子はこんな感じだ。これが、150ページぐらいで挫折した人の本の紹介だ。このあとに、多くのことが主張されているはずだが私は知らない。
もちろんこの本も読みかけで放置している。私は社会学を専攻していて、とくにこの分野を研究しようと思っているので近いうちに読み返そうと思うのだが、億劫だなあという気持ちが勝っている。怠惰なのだ。
ジル・ドゥルーズ・フェリックス・ガタリ「アンチ・オイディプス 上」p20 ぐらい
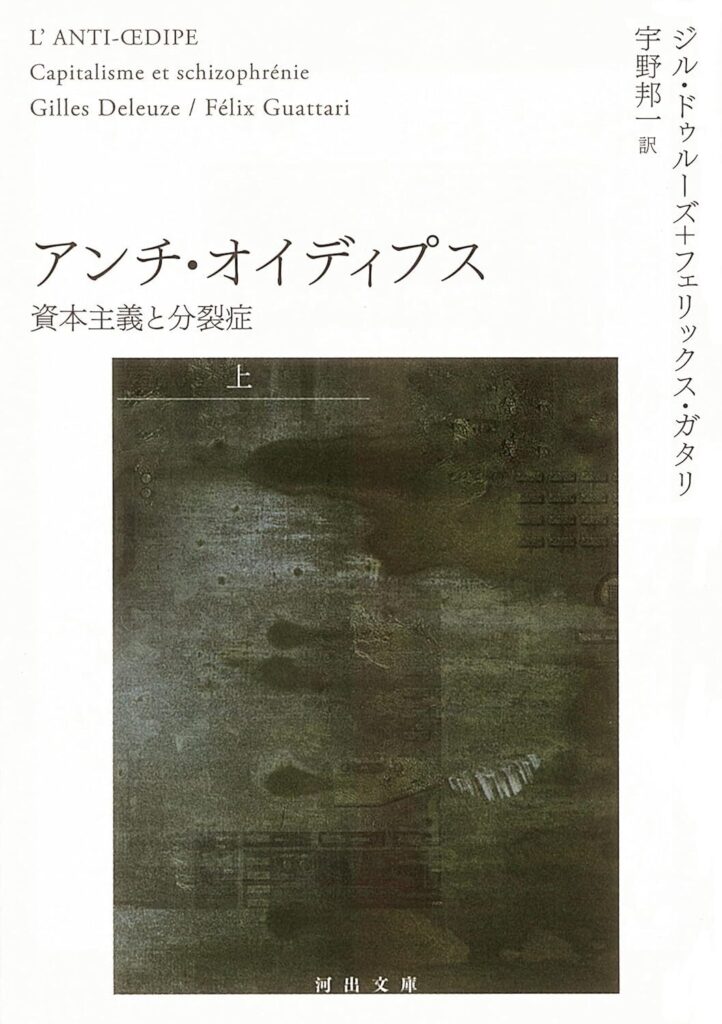
裁判長が、肛門日光浴する話。
裁判長が、
肛門日光浴
する話。
すごい要約をしてしまったが、私は最初に読んだ時はこれしか記憶に残らなかった。(ドゥルーズ・ガタリ好きの人は矛を鞘に戻してほしい)
「アンチ・オイディプス」は、心理学におけるエディプスコンプレックス(子供が父親に嫉妬心を抱くコンプレックス。母親を自分のものしたいと言う欲求)を批判した上で、最終的には資本主義にまで話が広がる現代思想の代表的な著作だ。
私はよし、読んでみようと思って手に取ったが、最初の文章の難しさに参ってしまった。
<それ>(エス)はいたるところで機能している。中断することなく、あるいは断続的に。<それ>は呼吸し、加熱し、食べる。<それ>は排便し、愛撫する。
ドゥルーズ・ガタリ(宇野邦一訳)「アンチ・オイディプス 上」p15
エスはフロイトの無意識に当たるらしい。だがそれでも訳わからない長続く。自分はフロイトの知識はほとんどないため、お手上げだった。それでも読んでいくと以下の文がある。
シュレーバー控訴院長は、尻の中に太陽光線をきらめかせる。これは太陽肛門である。
ドゥルーズ・ガタリ(宇野邦一訳)「アンチ・オイディプス 上」p15−16
私はこの文だけが印象に残った。やっていることは肛門日光浴だ。しかも控訴院長なんてたいそうな職についている人間が、肛門日光浴してる!
私は、少なくともこんなくだらない下ネタがこの本の本質ではないことはわかっていたので、仲正昌樹の「アンチ・オイディプス入門」を読んでみた。
その解説を読むと、シュレーバー控訴院長は、統合失調症にかかり、晩年その体験を手記にまとめる。その彼の症例についてフロイトやラカンも分析しており、バタイユも「太陽肛門」という著作を出している。
その流れがあってこその、肛門日光浴がある。
正直、アンチ・オイディプスはまだ「読みかけ」でなかなか読解に困難している。
でもこういう読書の仕方も悪くないのではないだろうか。私は無謀にも「アンチ・オイディプス」を読もうと試みた。けれど「肛門日光浴」なんて最低なワードを拾ってしまった。
だが、そのワードが、さらなる学びに運んでくれた。仲正昌樹の「アンチ・オイディプス入門」に辿り着いた。
はたから見たらいい加減な「読みかけ本」が、確かに役に立ったのだ。
先ほど、私はアンチ読書マッチョイズムにも反対すると述べた。もし、アンチ読書マッチョイズムなら、ドゥルーズ・ガタリ「アンチ・オイディプス」なんて本は間違いなく読むな、違う入門書を読め!というに違いない。
でも、私の「アンチ・オイディプス」の読みかけについては良い読書経験だったと思う。読書筋力が足りなくて読みきれない本を手に取って読んでも、それはそれで良い読書経験だ。
別に、読書なんて自由だろう。
まとめ
以上、読書についての話をしてきた。
私が提案したいのは、積読本より解像度を上げたカテゴリー「読みかけ本」だ。
「読みかけ本」のメリットは、読書自体を「半身」にすることができる。読書に残る特別性、特権性を厄払いすることができる。
別に無理に本を読み切る必要はない。読んだところから良い学びを得るなり、「アンチ・オイディプス」は肛門日光浴する裁判長の出てくる話だと勘違いしても良い。
ありきたりなことを言うなら、読書はひとそれぞれの読み方がある。同じ文章でも、読み取れるものが違う。
文章は正しい意味で読まなくてはならないという人もいるだろう。でも、人は本を読む時何かしらの文脈に繋げて読んでいく。今まで読んだもの、自分の経験、多くのフィルターを通して読む。そこで、何か面白い発見があればいいのだ。
本が読めない人は、ひとまずハードルを下げて読書を始めることが重要だ。本当にありきたりなことだが。
では、最後に「読みかけ本」式読書術をまとめてみよう。
1 好きな本を買って読んでみよう。難しい本でも構わない。読みきれないなら「読みかけ本」にしてしまおう。
2 その著作に関連する入門書や新書に手を出してみよう。
3 その入門書も「読みかけ」にしても構わない。
4 たくさんの本を「読みかけ本」にしよう。
5 いつか、「読みかけ本」に戻ってきて、その本を読み切ってみよう。
6 戻っても読めなさそうなら、またしばらく寝かそう。
読書法としてはありきたりだと思う。新規性はない。
世間には多くの読書術があるけれど、どれも万人に適応できる技術ではない。自分のこの読書術も万能ではないだろう。どうやれば本が読めるか、個人が模索する必要もある。
好きな本を買って読んでみる。「読みかけ本」読書術の1が最強の読書法だ。
読書が特別な営みであるという幻想を厄払いする、それが一番の読書術だと私は思う。
蓮見スイの「読みかけ本」リスト
投稿者プロフィール
- zinbun運営者 早稲田大学文化構想学部
X(旧twitter)
最新の投稿


 記事2025年2月28日Webメディア zinbun宣言
記事2025年2月28日Webメディア zinbun宣言