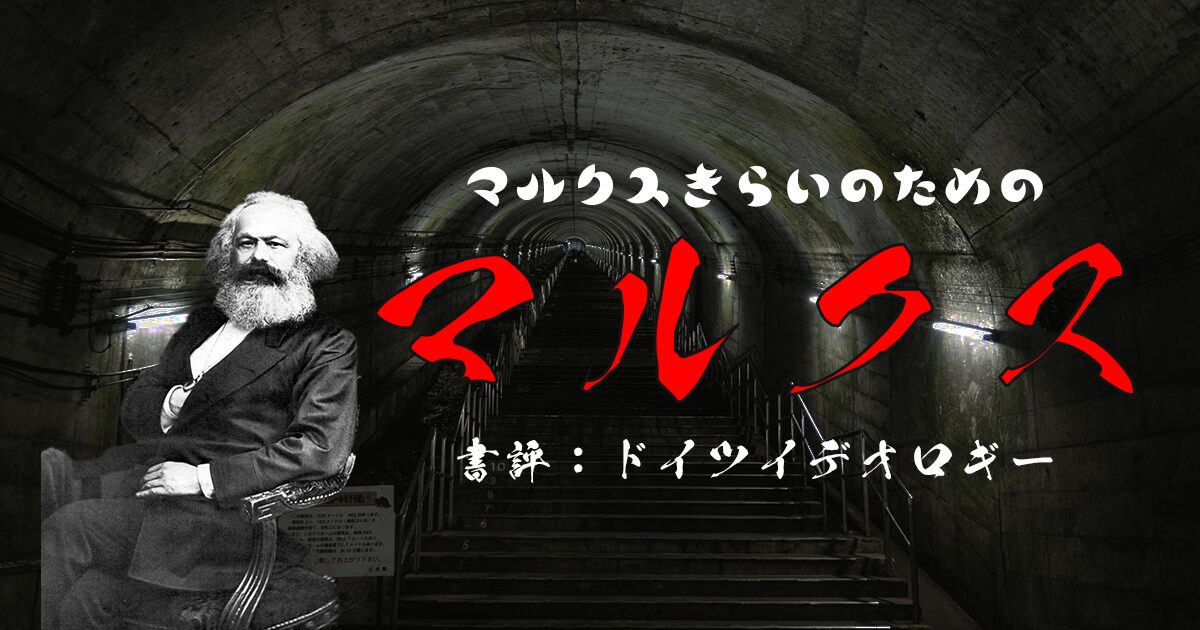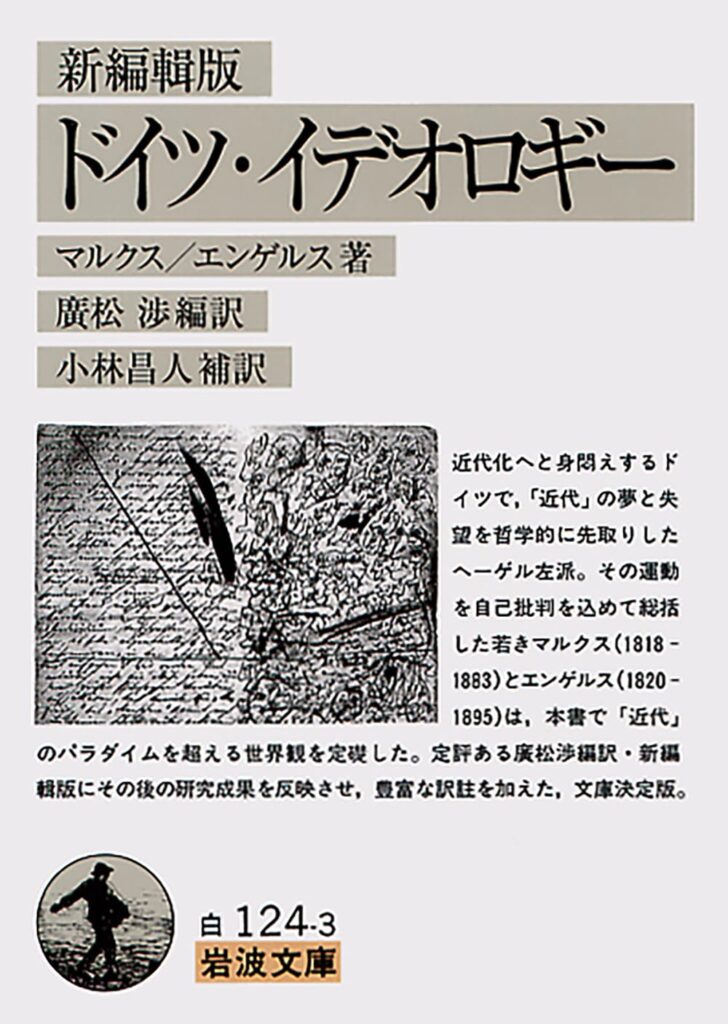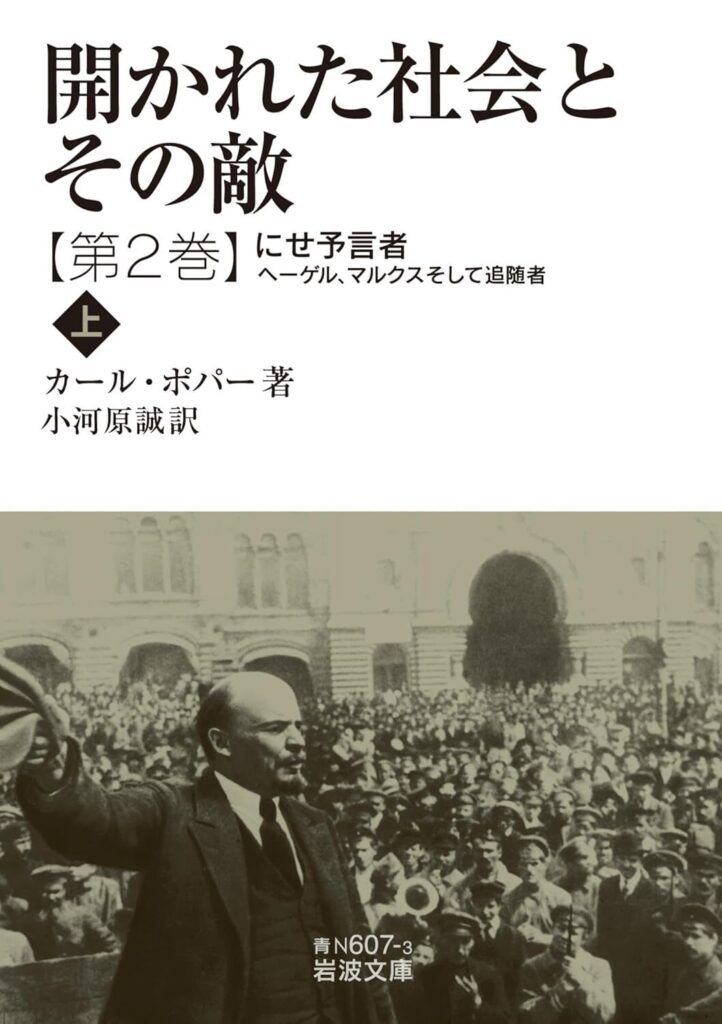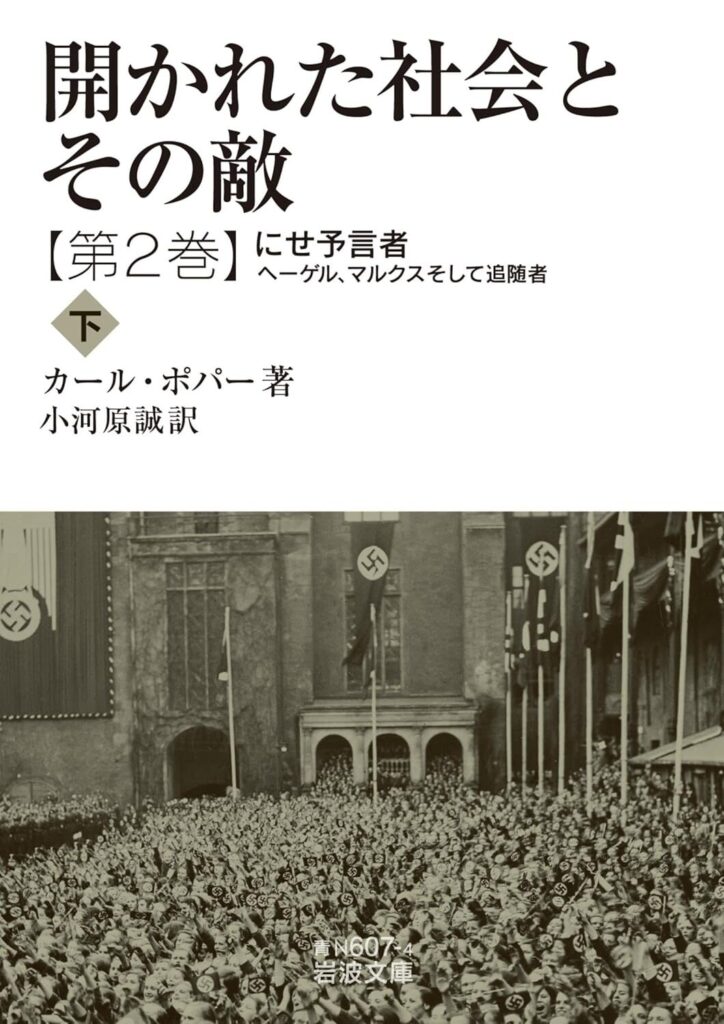マルクス主義と聞いて、多くの日本人は何をイメージするだろうか。「ああ、あれね。過激派の思想。左翼でしょ」、「米ソ冷戦によって崩壊した社会主義の理論だよね。現代でもハマる奴は馬鹿だなあ」。こんな声が聞こえてくる。
彼らは、マルクス主義について、それが左翼の論理であり、ソ連成立などに影響を与えた事は知っている。ただ、どちらも、それが取るに足らないものとして扱っているのだ。しかし、この二つの声は既に重要な観点を含んでいるのである。
もし、前者の人の言うように、過激派と恐れられつつ、後者の人が言うように、死んだ思想としてマルクス主義があるのなら、なぜ現代の若者でも、マルクスに傾倒するものは後を絶たないのだろうか。
もしくは、質問を変えよう。もし、マルクス主義を信奉する若者があなたの目の前に現れて、マルクス主義に基づく議論を展開したら、あなたは彼らに言い返す言葉を持っているだろうか。
この二つの質問で私が言いたいことは、つまるところ、マルクス主義が一つの強固な理論体系であり、現代においても通用する議論を展開できてしまうという事である。
もし、あなたがふと入った大学で、マルクス主義の若者から勧誘を受けたとする。もし上記のような認識しか持たないと、マルクス主義の内在論理に魅了され、コロッと転向してしまった、などという事が起こり得るのである。
さて、マルクス主義団体が危険かどうか、もしくはマルクス主義が正しいかはここでは問わない。としても、単に自らの知識不足で、大きな世界観に魅了されてしまう可能性があるというのは、なんだか足下が心配になってこないだろうか。
もし、マルキストになるのだとしても、自ら論理をじっくり検討した上でなるのと、主義者の高等な思弁にサクッと懐柔されてしまうのでは、大きく違うと思わないか。そうでなくても、20世紀最大の思想家と言われるマルクスについて、一度は学んでみるのは良い試みではないか。
マルクスの論理をじっくり検討するには、まずマルクスの著書そのものにアクセスするという方法が考えられる。しかし、マルクスの理論だけを学ぶというのも、一つマルクスに呑み込まれる恐れがある。それを回避するためには、他の理論書や、マルクス批判書なども併せて読むというのがベストに思える。
ただ、私がここで提案したいのは、マルクスが何を前提としているかを踏まえて、批判的に読むという手法である。というのも、マルクス理論は、理論基板が比較的分かりやすい方で、そこを疑うという視点を持てば、折衷的な受容が出来るように思えるからである。これは、高度な批判的思考を持つ若者などには是非ともお勧めしたい方法である。
今回、紹介する本は、『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』(岩波文庫)である。
本書は,ヘーゲル左派運動の総括として,マルクスとエンゲルスが自己批判をも込めて共同で執筆した未完の遺稿で,「唯物史観誕生の書」とも呼ばれている.本書は遺稿ゆえに種々のテキスト問題を抱えているが,今回厳密なテキストクリティークをし,信頼に足る邦訳の完成を目指した.文庫版ということも鑑み,読みやすさも追求した決定版.
岩波文庫ホームページの紹介文
この本を理解するためには簡単な前提知識が必要である。
一つは、マルクスとエンゲルスは、ヘーゲルという偉大な哲学者の体系を元に出発しており、ヘーゲル左派の人物であったこと。
そして、ヘーゲル左派はヘーゲルの観念論(大まかに言って、観念が物質に先行するという論)に反対し、唯物論(大まかに言って、物質が観念に先行するという論)を主張したということ。
そのため、従来の観念論的ヘーゲル解釈をする、ヘーゲル右派と対立していたこと。
そして、ヘーゲルの止揚(アウフヘーベン/弁証法)哲学を、唯物論的に応用したということ、である。止揚、とは、二つの矛盾している命題を、一個上の次元で統合する手法の事を指す。
それを踏まえて本書を見ていこう。まず、本質的なマルクスの考えを引用で提示する。
(…)フォイエルバッハはプロテスタンティズムを説明し、その後に自立的な哲学史を無理なく続ける。
ドイツ・イデオロギー p226
(e)「存在とは、普遍的な、諸事物から分離できるような概念ではない。それは、存在しているものと一体である。……存在は本質の定立である。」(…)
君の心胸の存在するところ、そこにのみ君は存在する。そして、あらゆる事物は──自然に反する場合を除いて──それが現に存在するところに存在しようとし、現にそれであるところのものであろうとするのである。」四十七ページ。現存するものへの麗しき讚辞。自然に反する場合や、僅かな、異常な場合を除けば、君は、好んで七歳にして炭鉱の抗口番に就き、独り暗闇の中に十四時間もいたがる。それが君の存在なのだから、したがってまた君の本質でもあるのだ。
批判対象となっているフォイエルバッハが何を言ってるのかはともかく、ここではマルクスの主張ははっきりしている。
ここでのマルクスの言い回しは、反語表現、つまり皮肉である。即ち、存在論に関する哲学は、現実の問題──物質的な問題──を前にして、酷くナンセンスだということだ。ここでマルクスが打ち立てようとしているのは、まさに、「炭鉱の坑口番で、十四時間も暗闇にいなくて済む」ための思想なのである。
すべてこれらは、純然たる思想の内部でなされたという。〈世俗的な外界はこれについて、もちろん何事も経験しなかった。というのも、世界を震撼させる事件全体の行き着いた先が、絶対精神の腐《敗》朽過程でしかなかったからである。〉たしかに、ことの眼目は絶対精神の腐朽過程という興味深い出来事にある。
ドイツ・イデオロギー p21
絶対精神とは、ヘーゲル哲学における重要概念で、人間の意識の最終到達点である。意識は、弁証法という、二つの矛盾した認識の統合を繰り返し、最終的に全ての矛盾が統合された絶対精神に辿り着く。そして、絶対精神とは世界意識でもあり、歴史はこの絶対精神を実現していく過程と解釈される。
この説明だけではよく分からないだろうが、要するに、「最強の精神」を実現しようとするのがヘーゲル哲学である。
これに対してマルクスは言う。現実を見ろ。労働者は極めて過酷な状態に置かれ、資本家はますます搾取を強める。歴史とは絶対精神を完成させていく過程?そんな事は、現実を見れば極めてどうでもいいことだ。
そして、マルクスは、歴史とは最終的にどこに向かっているかを、ヘーゲルがしたように提示する。
※ここから極めて難解な引用になるが、後に解説するので、ひとまず流し読みされるように。
共産主義というのは、僕らにとって創出されるべき一つの状態、それに則って現実が正されるべき一つの理想ではない。僕らが共産主義と呼ぶのは、〈実[践的な]〉現在の状態を止揚する現実的な運動だ。(…)
ドイツ・イデオロギー p72
この「疎外」──哲学者たちに分かるようにこの言葉を用い続ければ──は、もちろん、二つの実践的な前提下のみで止揚されうる。それが「耐え難い」威力、つまり、人々がそれに反抗して革命を起こすような威力となるためには、それが人類の大多数をまったくの「無所有者」として、しかも同時に、現前する富と教養──どちらも生産力の巨大な上昇とその高度な発展を前提とする──の世界との矛盾において、創出してしまっていることが必要である。(…)
つまり、生産能力の発展なしには、欠乏、窮迫が普遍化されるにすぎず、それゆえ、窮迫に伴って必要物をめぐる抗争も再燃し、古い汚物がことごとく蘇らざるをえないだろうからであり、(…)したがって、一方では「無所有」の大衆という現象〈が〉をあらゆる諸国民のうちに同時的に〈現れ〉創出し(普遍的競争)、どの国民もが他国民の変革に依存するようにさせ
〈るからである。このことなしには〉、そしてついには世界史的な、経験的に全般的な諸国人を局所的な諸個人にとって代わらせることとなる──からである。このことなしには、(一)共産主義は局地的なものとしてしか実存しえず、(二)交通の〈疎遠な〉諸威力そのものが全般的な、それゆえに耐え難いほどの諸威力として発展してしまうこともありえず、土着的・迷信的な「厄介事」のままであり続けるであろう。
大変な長文引用で、しかも難解なので、ここで挫折してしまわないようにしっかり解説しよう。まず、ここでの「疎外」とは、分業によって、個人個人が自らの労働の主体ではなく、機械のようになってしまう現象を指す。これを「止揚」して解決するには、以下の二つの条件が必要だという。意訳してみよう。
①人類の大多数が無所有者になる
つまり、生産手段を何も持たないものが大多数となる
②それと同時に、富と教養は世界にある
めちゃくちゃ世界は発展している
この二つの矛盾が統合されると、共産主義社会は実現する、というのである。ここで前提とされているのは、一方に、「無限」とも言える富があり、一方に「虚無」を持つ大量の人間がおり、この二つが止揚される。
このような終末的な世界においてしか、共産主義という人類の最終状態は実現しないということである。そして、ここで前提とされているのは、局所的な共産主義革命が、交通により波及していき、最終的に世界革命に結びつくという過程である。では、この最終的な共産主義社会とは、どのような社会だろうか。
共産主義社会においては社会が生産の全般を規制しており、まさしくそのゆえに可能になることなのだが、私は今日はこれを、明日はあれをし、朝は〈靴屋〉狩をし、〈そして昼[には]〉午後は〈庭師〉漁をし、夕方には〈俳優である〉家畜を追い、そして食後には批判をする──漁師、漁夫、〈あるいは〉牧人あるいは批判家になることなく、私の好きなようにそうすることができるようになるのである。
ドイツ・イデオロギー p67
理想社会の到来だ。分業が廃止されるのである。
マルクスがこのような理想社会の到来のために、我々は何をすべきと述べたかは、実際にマルクスの著作に入っていき探求して頂きたい。
ただ、ここで、マルクス思想の前提というのは明らかにされたように思うのである。
それは、極めてこの世の終わり的な、大多数の無所有者と、一部の富との止揚が、最終的に起こり得るという確信に立って理論が展開されたのがマルクス主義ということだ。
では、この前提は何に依拠するのであろう。それは、生産体制の発展により、究極的には大多数は無所有者にまで行き着くということだ。しかし、ここには疑問を挟む余地は大いにあるのである。
例えば、この革命理論を阻止するために、再分配を繰り返していけば、ずっと均衡が続き、このような社会には辿り着かないのではないか?もしくは、いつかはこうなるかもしれないが、その前に、大量破壊により人類が絶滅するという可能性は?
このように、マルクスの歴史観(唯物史観)そのものに疑問を呈するアプローチは可能なのである。その上で、このような社会の実現を信じるかどうかは、あなた次第、と言ったところになるのではないか。
本書は、マルクスの唯物史観を知る上で必携であり、また翻訳が極めて読みやすい。古典名著として、ぜひ一度は読むべき書籍。
また、唯物史観の批判について知りたい方には、以下の書籍をおすすめする。
開かれた社会とその敵 第二巻 にせ予言者――ヘーゲル、マルクスそして追随者(上) (岩波文庫) カール ポパー (著), 小河原 誠 (翻訳)
開かれた社会とその敵 第二巻 にせ予言者――ヘーゲル、マルクスそして追随者(下) (岩波文庫) カール ポパー (著), 小河原 誠 (翻訳)
※本記事はアフィリエイト収益を得ています。収益は運営、原稿料の支払いに充てられます。
投稿者プロフィール

- 地方大学2年生。心理系学部。キリスト教、哲学、神秘主義に詳しい。プラトン、アウグスティヌス、内村鑑三、キルケゴール等が愛読書。
SNS
X(旧twitter)
最新の投稿