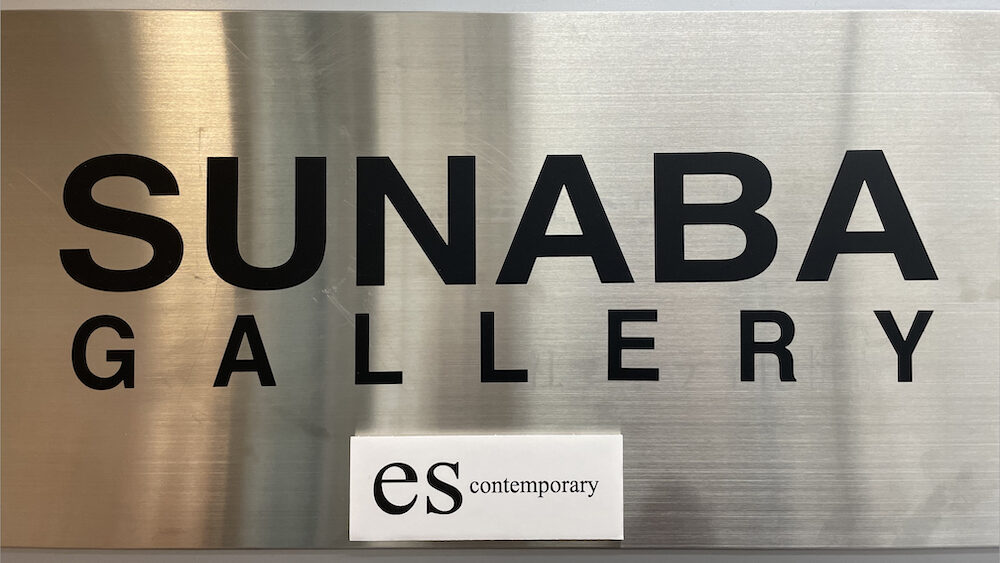二十年ほど前に『アエラ』や『美術手帖』などに美術評を書くようになり、サブカルまじりの美術論集をいくつか出したあと、今度は「SUNABAギャラリー」なる店を構えて画商になった私は、学究の徒とはとうてい言えない。むしろ学問から逃走し続けているうち、還暦が目前に迫っているという人間である。そんな自分に、人文学のwebメディアなる立派な場所に書く資格はあるか。それが本稿の問いである。
人文学、と聞いて思い浮かぶのは、あれやこれやの専門科目の講義や人文書のことではなく、遠い昔、大学に入りたての頃に受けた、語学の授業のことである。詳しい内容はうろ覚えだが、当時受けたショックだけは、いまも脳裏に焼き付いている。
私が通っていたのは中堅どころの私大だったが、語学がやたら厳しい学校で、あるコマではいきなりシェイクスピアを読まされた。シェイクスピアの戯曲に出てくる英語というのは、江戸時代の日本語と現代日本語が異なるように、現代英語とは文法や語彙がちょくちょく違っている。二人称代名詞のthouだのbe動詞のartだの、聞いたこともない単語がいきなり出てきて、なんの解説もないまま話が進む。周りを見回すとそれで苦労しているふうもなく、正直、えらい学校に入ったと思ったがあとの祭りだった。
他のコマではイタリアの画家で美術史家であるジョルジョ・ヴァザーリの『芸術家列伝』、その英訳本を読まされた。こちらは現代英語で書かれてはいたが、中身はルネサンスの芸術家の伝記で、美術史が頭に入っていないと何の話かすらわからない。訳の説明のあと本文へのコメントを先生が話してくれるのだが、中身はディゼーニョ・インテルノ、つまりはルネサンス期の「内的構想」についての解説で、現代風にいうなら美術作品のコンセプト立案に関する議論だ。個々の作家、作品は当然知っているものとして完全スルー、その発想法が講義の焦点なのである。しかも背景には当時の新プラトン主義哲学の考え方があるようで、哲学方面の知識もある程度ないと五里霧中という難物だった。
もう一つ苦労させられたのは、ジェームズ・ジョイスの短編集『ダブリン市民』を読む授業だった。この授業では学生が本文を訳していくが、単に訳すだけではダメで、そのパラグラフが構造論的に何を意味するのか、その分析までやって来ないと先生のカミナリが落ちる。作中に登場する泥のモチーフとは何を意味するのか、主人公の名前がマライアなのはなぜか。なぜその息子はコルク抜きを泣きながら探すのか。一年かけて分析するうち、平凡な中年女性の誕生パーティーについての短編小説が、聖処女の被昇天説話に変わってしまうという講義だった。
とはいえ、なにせ当時の自分の読書といえば、夏目漱石に太宰治、三島由紀夫に大江健三郎といった日本近代文学の保守本流ばかりで、ジョイスなんか読んだこともない。たまたま別の授業で文化人類学の手解きを受けていて、構造分析の勘所は薄ぼんやりと知っていたから、どうにかこうにか答えられたが、いま思い出しても冷や汗が出る。
このほか、なぜかドイツの中世の大学史について英語のテキストを毎回読まされるという授業もあった。おそらく社会史に興味をお持ちの先生だったのだろう。要するにどの先生も、いちおうは語学の授業のテイこそとっているものの、実際にはご自身の関心分野の英語論文をテキストにして、学生と一緒に読んでいたのだと思う。
高校生の頃の私は、文学部というのは小説だとか美術だとか、要は文化的な表現物が好きな人の行くところだと思っていた。英文学が好きなら英文科、歴史好きなら歴史学科、美術が好きなら美学科、といった具合だ。それでも概ね間違いはないのだろうが、授業を受けるうちにわかってきたのは、要は文学部というのは「人文学=ヒューマニティーズ」、つまりちまちまとした「お芸術」を学ぶのでなく、「人間そのもの」を学ぶ学部なのだということだった。
そんなの当たり前だと思う方も少なくないだろうが、九州の高校を出たばかりの自分にとっては、まったく目が覚めるような驚きだった。人文学では文化表象はもちろん人間の営みすべて、つまりは「人間性=ヒューマニティー」を学び、解き明かすことが目的とされているのだと、今さらながらに気づいたのだ。文学などの文化的表現物の理解はその一部でしかなく、めざすはレオナルド・ダ・ヴィンチのような普遍人、万能人としての普遍知の獲得だったのだ。
人間の営みすべてが対象である以上、これは英文学、これは人類学、これは哲学といったタテ割り知識での対応で済ます訳にはいかない。人間についての学知を総動員し、人間というもっとも身近でありながら、最大の謎でもある存在に挑む。そうした総力戦こそが人文学なのだ。したがって美術を学ぶには哲学の、英文学を学ぶには構造分析の知識が必要となり、逆もまたしかりとなる。要は無数のリンクが各ジャンル間に縦横に張られている世界だと気づいたわけだ。
しかもどうやら人文学、ヒューマニティーズの淵源を辿れば、リベラルアーツすなわちルネサンス期の自由七学芸という、学問の化け物みたいなラスボスに辿り着くのだとも知った。リベラルアーツになると人文系ばかりでなく、数学や占星術、果ては音楽まで含む。要はすべての学問を修めてなくてはいけない修羅の道なのだ。先生によってはヒューマニティーズを知らんというのは人間を知らんということ、すなわち人間ではないということだよ、なんて脅かす先生もいた。
こうしたことに朧げながら気がつけたのは、いま思うと語学のプログラムが情け容赦ない水準のものだったからで、私のような劣等生でも、文学部とは、人文学とは何かということを、いやでも体で理解せざるを得ない組み立てになっていた。いま思い返してもスパルタ式の教え方である。
その後、院への進学も考えたこともあったにはあったが、美学の院生がギリシャ語のテキストを輪講しているのを見て、こりゃ到底ついていけないと思って遁走した。金銭的な都合もあったが、正直、能力的に無理だと思って逃げ出したのだ。
ここで話は冒頭の問いに戻る。学問から逃走し続けている自分に、人文学のwebメディアなる立派な場所に書く資格はあるか。「ない」と答えそうになる自分を叱咤し、あえて蛮勇を振るって書く理由はといえば、まさに学生時代に先生方からいただいた脅し文句、「ヒューマニティーズを知らぬ者、人間にあらず」というあの言葉を、いまさら思い出したからだ。
途方もない領域にまたがる学知を総動員する人文学を、還暦を前にいまさら学び尽くすことなど、日暮れてなお遠し、もう無理に違いあるまい。だが、せめてその片鱗でも学び直し、ヒューマニティーズの断片だけでも身につけて、人間として死にたい。そんなふうに考えたのである。
とはいえ日々の業務の隙間時間で執筆することになるので、果たしてお役に立てるかどうか。むしろ足を引っ張るのが関の山だろうし、多くの方にご迷惑をおかけすることだろう。が、在野の方も是非という主催者の方の言葉をあえて素のまま信じて、ここに愚考を開陳する次第である。
投稿者プロフィール

- 1967年、福岡県生まれ。SUNABAギャラリー代表、文筆家。関西学院大学文学部美学科卒。PR会社勤務を経て2000年より執筆活動開始。2015年4月、SUNABAギャラリー開業。単著に『恐怖の美学~なぜ人はゾクゾクしたいのか』(2022、アトリエサード)、『ソドムの百二十冊 ―エロティシズムの図書館―』(2016、青土社)、『真夜中の博物館 美と幻想のヴンダーカンマー』(2014、アトリエサード)、『死想の血統 ゴシック・ロリータの系譜学』(2007、冬弓舎)。共著多数。
SNS
X(旧twitter)
最新の投稿
 記事2025年3月15日人文学再入門 ~還暦まぢかの人文学~
記事2025年3月15日人文学再入門 ~還暦まぢかの人文学~