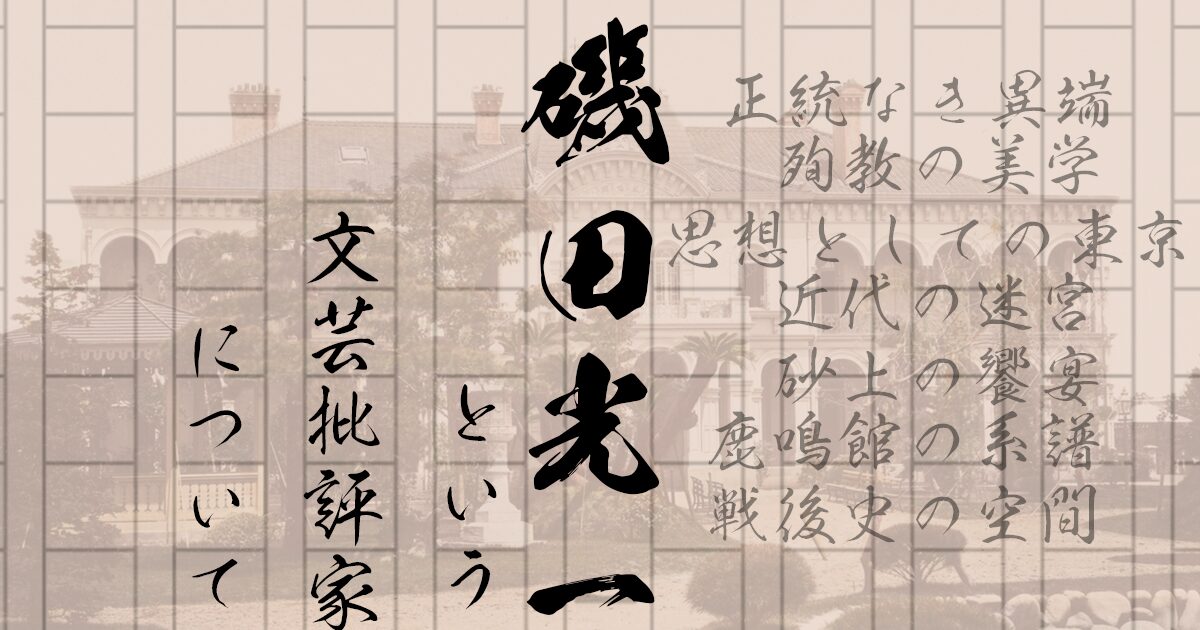磯田光一という文芸批評家を語る際に、私の中でいつも第一に脳内に浮かぶことは、この人以上にニュートラルという感覚が文体から伝わってくる人も中々いないということである。個人が文章で表現する際には、何らかの私的思想が強く表れる。高度な知識を身に着け、多くの物事に精通している人ほど、何かついつい自分の信念へと文章内で読者を誘導したくなるものだ。それは作家も例外ではない。
さて、急に話が文学史に飛んでしまい申し訳ないが、そもそも、戦後すぐの日本文学界は敗戦のショックにより、反省と新しい時代の適応に慌てふためきながらスタートした。多くの作家が、戦中の自分と戦後の自分をフィックスするために知恵を働かせて、作品作りや座談会に臨んでいたのだ。
勿論、「近代文学」の座談会でそういった態度の知識人がとる、過剰な適応や反省に対する批判を試みた小林秀雄や、戦前から戦後にかけても鷹揚たる個人主義を崩さなかった永井荷風など、思想の足元を崩されなかった人々もいるが少数派であった。
そんな、戦後に思春期を過ごし、高度経済成長の時期に文壇に登場したのが磯田光一であった。先輩にあたる人々が前代未聞の思想的態度の困惑に陥っているのをリアルタイムで見て、育ってきた世代の彼は、同世代の江藤淳・石原慎太郎(彼らは60年安保闘争以前に文壇デビューしているが)といった、作家・評論家と共に昭和の中期から後期にかけて豊富な作家論と(近代や現代と深く結びついた)文学論を上梓していく。
三島由紀夫 、永井荷風 、萩原朔太郎 といった文学史に於けるユニークな作家をピックアップした作家論から、戦後論と文学論が深く結びついた「戦後史の空間」 や日本の近代化について鋭く論考した「鹿鳴館の系譜」 など、前述したように彼が残した作品は作家論から、文学論の枠をはみ出た、包括的文化論と言える著作まで幅広い。
作家論からはその批評対象に対する強い愛は感じる(三島由紀夫には特に強い思い入れを感じる)が、過度に自己をその作家や作品に同一化するような耽溺はさせずに、愛しているが故に冷静な敬意を払い、情熱的なのに決して飲み込まれないように筆致を守り続ける態度は彼の作家論の文体に特徴的なものである。
その、一方で文学論や文化論には作家から政治家。右派から左派まで、バラエティ豊かな人物が登場し、彼の文章内での思想的深まりのお供をしてくれる。しかし、彼はその誰にも肩入れをしようとせずに、中立的な立場を崩さない。一定の立場や思想に理解はしても、同志になることは意識して避けているようにその文章からは伺える。
例えば、「鹿鳴館の系譜」の中で二葉亭四迷の浮雲の主人公である内海文三について以下のように語り、日本近代の精神の一つの形について述べる。
内海文三は疑いもなく二葉亭の内心の想いを託した近代小説の人物である。他の人物がことごとく外部の事象や利害に動かされているのに、文三だけは「内面」に固有の論理を所有しているからである。それが社会的な功利性には還元できないものであるという点で、文三は開花の世相にそむいた精神主義者と呼ぶにふさわしい。
磯田 光一『鹿鳴館の系譜』収録「東京外国語学校の位置」(講談社 1991)p113~114
近代の精神の形を小説の中の個人に見出した、すっきりとした文章であり、近代讃美者でもなければ、反近代主義者でもない、冷静に明治という近代を「浮雲」という名作の中に見出そうとしている磯田のスタンスが文章から見出せる。
また、「思想としての東京」でも近代の問題に触れている。
漱石はいまの多くの知識人たちとはちがって、”開花”を体制の強制した悪だなどと考えるようなオプティミストではなかった。東京人として生まれながら、”東京方言”を滅ぼしていく現実を「欠くべからざる」ものと認め、その必然が個体に強いた乖離感から厭世の思想を語ったのである。
磯田 光一『思想としての東京』収録「思想としての東京」(講談社 1990)p68
大文学者・夏目漱石が近代開花を感じるうえで感じたジレンマを見事に掬い取り、我々に偏りなく伝えている。その一方で、漱石が単なる反近代主義者でないということも文中でしっかりと補正してある。このように、磯田の文体はスムーズであり、何か極端なとっかかりがなく、引用文だけでもすっきりとわかりやすい。
磯田がこのような情熱的なのに中立。という、処世術も必要とする技術を持ち、バランス感覚を文壇の世界で最後まで崩さなかったのは驚嘆に値すると私は思うのだ。
人文学の世界に少しでも踏み込んでみれば、そこには膨大な思想やイデオロギーが存在している。時には、自分の信条とは相容れない考え方も山ほどある。私もそんな経験の連続であり、一時は人文学の世界から離れ、ただの娯楽耽溺者に堕することも考えた。しかし、そんな中で、私は、小林秀雄、福田恆存、江藤淳といった近代や戦後に疑念の目を向ける、時流に棹をさすことをよしとしない文学者たちから大きな勇気を貰い、今回とりあげた磯田光一に出会ったのである。
人文の世界は個性的な哲学者や、難解さが魅力のポストモダン思想家たちだけのものではない。特に文学は、読書という私たちにとって非常に身近な行為と密接に関わっており、人生で一番最初に接する人文学といってもよいかもしれないのだ。
読書感想文から始まり、ブログやSNSに感想を書き込む行為に至るまで、実は社会には文芸批評の一歩手前の行為にあふれている。最早、文学に於ける批評行為はかつてのような、膨大な読書量と豊富な文芸の知識に裏打ちされた一部の作家や批評家のものではなく、まだ広く世に知られていないだけで優れた感性を持つ、電子空間を揺蕩う多くのアマチュアに支えられているのかもしれない(これは批評全般に言えることではあるが)
アマチュアの一人として、昭和期に活躍したプロフェッショナルの一人である磯田光一を、この場をお借りして紹介するのも何だか恐縮な気がする。けれども、主観と個人の感性によって大きな声で批評をする方がたくさんの人に届きやすい昨今、磯田のニュートラルで情熱的な態度は非常に新鮮であり、それは今後の批評においても求められることだと、私は改めて思うのだ。
磯田光一の著作は、現在絶版などが多く入手するのが難しいが、それでも読む価値があると思っている。
現在、簡単に読む方法は国立国会図書館デジタルアーカイブだ。利用者登録を済ませていれば磯田光一の著作をネットで自由に読むことができる。
・思想としての東京 : 近代文学史論ノート https://dl.ndl.go.jp/pid/12458591
・殉教の美学 : 磯田光一評論集 https://dl.ndl.go.jp/pid/12459444
・近代の迷宮 https://dl.ndl.go.jp/pid/12459305
投稿者プロフィール

- 文学からアニメまで幅広く、文系学問を好み、小林秀雄・福田恆存・江藤淳の三人を敬愛しています。
最新の投稿