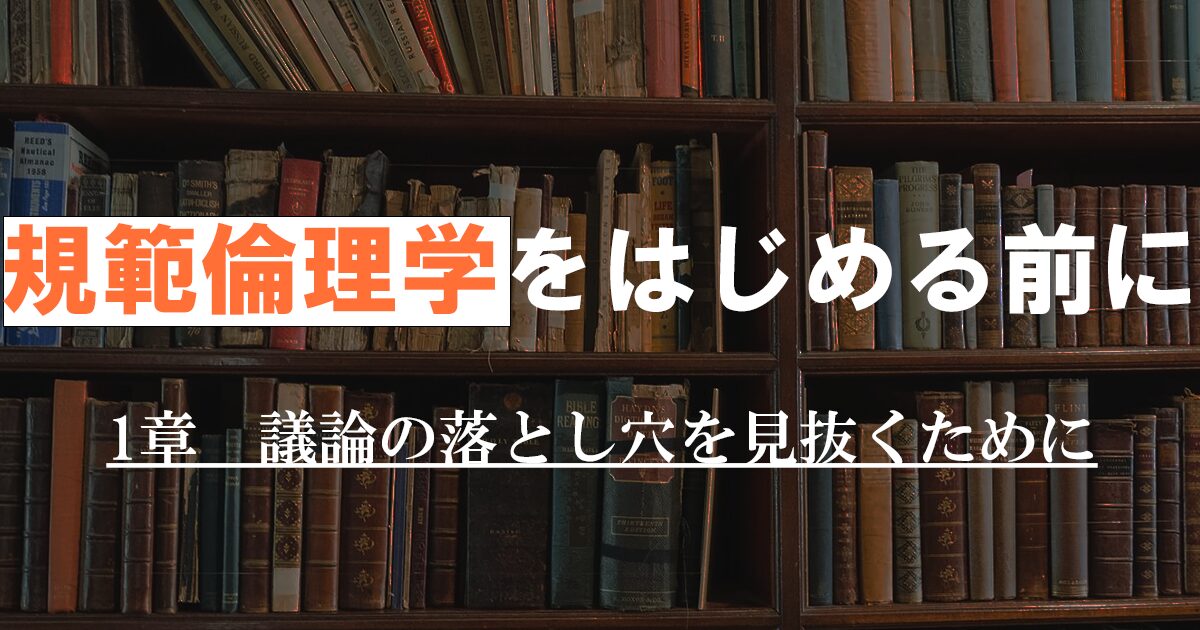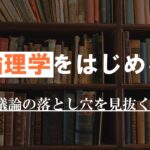はじめに
あなたは「道徳」という言葉にポジティブな印象を持っているだろうか?それは往々にして我々の行動を縛り、なんらか賞罰を与えるもの。明文化も実在もしていないくせして、誰かが押し付けてくるルール。日本では『善悪は人それぞれ』という相対主義が根強い。しかし「快楽のためだけに人を殺してはならない」「戦争は悪いことだ」など人それぞれなはずの考えを我々は広く共有し、しばしばそういった道徳的判断を下しているように思える。一体、道徳とはなんだろうか?それは何かしら客観的な確証を持てるものだろうか?一般化できるのか?体系立てて扱えるものだろうか?小学校の道徳の時間からはより進んだ道徳の世界。全てを疑って批判するほど歓迎されるめくるめく道徳の世界を覗いてみよう。
タイトルの倫理学というのは道徳哲学とも表され、文字通り道徳にまつわる現象、言明を研究する哲学の一分野である。多くの学問がそうであるように倫理学にも専門用語とディシプリンがある。このディシプリンを認識することで「トロッコ問題ですか?責任を負いたくないので引きません!」「道徳なんて実際人それぞれなんだから言っても仕方なくない?」などのナイーブな倫理観から抜け出すことができる。
したがって本稿では道徳を吟味、批判する倫理学の中でも特に規範倫理学をはじめる前に知っておきたい2つのことを扱う。まずハマりがちな落とし穴(誤謬)、そしてこの学問の道のりに付けられた柵の外側(形式的制約と決断)を知ることを目的とする。
話をはじめる前に規範倫理学という語が目新しい読者も予想される。そのため規範倫理学と倫理学は何が違うのか、本論に進む前に簡単な説明を挟もう。倫理学は大きくメタ倫理学・規範倫理学・応用倫理学に分けられる。
例えば「なぜ人を殺すことは悪いことなのか」という問いを考えよう。規範倫理学、倫理理論から「それは功利(人々全体の幸福)を減らす行為だから」「そのような格率は普遍的法則になりえず、義務に違反するから」などの回答が与えられる。
対してメタ倫理学は「そもそも悪いとはどのようなことか」「そのような義務は実在するのか」「なぜ道徳的義務に従う必要があるのか」などメタ(高次の、一歩引いた)視点から倫理学、道徳を批判する。規範倫理学は功利主義・義務論・徳倫理学など個人、社会に限らず包括的で普遍的な道徳的原理・原則を解き明かすことを目的とする。1
応用倫理学はこれらを踏まえて特に生命医療や環境、企業など個別具体的な分野で規範倫理学を応用する方法論や実践などを研究する。自然科学や企業の目的など倫理学の中でも特に異分野と密接にかかわる。
それでは本題に移ろう。本来一記事にまとめる心づもりであったが、複数記事に分割する。本稿一章は誤謬についてであり、児玉聡 『実践・倫理学』 (勁草書房,2020)を参考にした。
目次
1章 議論の落とし穴を見抜くために
1. 衆人に訴える誤謬
2.権威に訴える誤謬
3.ヒュームのギロチン
2章 倫理理論の形式的制約
1. 普遍性・不偏性(『統治と功利』参照) 議論の一貫性
2.倫理的に重要な違い
3.価値論、当為論 (人間観)
3章 公理の決断、倫理の意義
1. 偏愛
2.(善意志 (功利主義と義務論のバランスのために入れているが、割愛の可能性もあり))
3.道徳的で倫理的な生き方
1章 議論の落とし穴を見抜くために
倫理学をはじめるにあたって分かりやすい落とし穴、勘違いを挙げるならば誤謬だろう。誤謬とは端的にいえば推論の誤りのことであり、中でも分かりづらいものが初学者にとっての落とし穴になる。本章では「議論の落とし穴を見抜くために」と称して規範倫理学のなかで取り除かれるべき誤謬を挙げる。
1.衆人に訴える誤謬
典型的な誤謬が衆人に訴える誤謬である。このような会話を想像しよう。
A「日本で死刑制度は存続されるべきだと思うよ」
B「本当にそうかな?」
A「そうさ、内閣府が行った世論調査で死刑賛成派が反対派を下回ったことはないよ。
だから死刑制度は存続されるべきなんだ」
B「うん?なんだかおかしいぞ?」
Aの推論は妥当だろうか?そうではない。仮に世間の大多数が奴隷制を支持しようが、世界の飢餓を放っておくことが正しいと言おうが、それは道徳的言明を正当化するための論拠にあたらない。道徳的言明は重要であるため簡潔に説明しよう。「〜である」「〜だ」という文は事実言明、記述言明と呼ばれる。これに対して「〜は悪い」「〜はすべきでない」などの文章が道徳的言明にあたる。
少し進んだ補足をすると道徳的言明は主に価値に関する言明 「~は善い/悪い(good/bad)」である価値判断とすべき行為(当為)に関する「~は正しい(right)」「~すべきだ(ought)」などの当為言明の二つに分けられ、任意の倫理理論は価値言明と当為言明が体系的に構築された価値論・当為論で構成される必要がある。
このような道徳的言明の根拠に多数決や大多数の意見を持ち出すことはむしろ誤謬、誤った推論になる。このように学問的ないし倫理的な議論や問い、命題の是非は多数決や衆人の賛否によって決まるものではないことが理解していただけただろう。
最後に衆人に訴える誤謬に関して、その精神的な源流は『クリトン』によく表れている。
(ソクラテスはアテネの陪審員によって、涜神罪2で死刑が確定した。そんな君が甘んじて死刑を受け入れれば、君と僕は世間からの非難を免れないだろう、だから死刑から逃げ出すべきだと説得するクリトンに対して)
ソクラテス :それじゃあ、例えば次の場合について僕達の主張はどうだったろう。いったい運動術を練習してこれを本職とする人は、あらゆる人の賞賛や非難や意見に重きを置くだろうか、それともただ一人の人の、すなわちその医者とかその体育教師とかいう者の意見ばかりを重んずるだろうか。
クリトン :ただ一人の人のだけだ。
ソクラテス :すると彼の畏るべきはただその一人の人の非難であり、また彼の喜ぶべきは、その賞賛であって、彼は多衆の非難や賞賛を気にしてはならないのだね。
クリトン :その通りだ。
ソクラテス :よろしい。ところが彼がもしこの一人の人に対する服従を拒んで、その意見と賞賛とを蔑視して、かえって素人である多衆の意見を重視するとすれば、その結果彼は禍を蒙りはすまいかね。
クリトン :無論さ。
『ソクラテスの弁明 クリトン』 久保勉訳(岩波文庫,1964)p.82-83
ここで道徳的に重要な一人としてソクラテスが想定しているのは神のことだが、現代においては信頼のできる理性を持った他者、道徳哲学者になるだろう。
注意が必要なのは、倫理学は世間一般の常識や道徳的な言明の一切を無視してよいという意味ではないことである。例えば「トロッコ問題でレバーを引かない人が多い」という事実言明は「(ゆえに)レバーを引かないことが正しい」という道徳的言明の論拠にはならない。しかし「(ゆえに)レバーを引くことが正しいという主張の啓蒙は漸進的に行われるべきである」という道徳的言明を導くさいの根拠にはなりうる。
2.権威に訴える誤謬
同じように権威に訴えることも道徳的言明の論拠たりえない。例えば中絶を認めるべきか。安楽死は正しいことか。という規範的な問いに対して「母体保護法がダメだと言っているからダメだ」「最高裁判決でもこのように言っているから道徳的にも認められないだろう」というのは回答の根拠にはならない。倫理・道徳は法や国家、権威に先立つものであるためだ。
3.ヒュームのギロチン(方法二元論)
これが恐らく最大の誤謬であり、メタ倫理学にも密接にかかわるものであり、ゆえに最も重要なものである。ヒュームのギロチンとは、「事実言明のみから道徳的言明は論理的に妥当な形で導き出されない」というものだ。
具体例を考えよう。まず、論理的に妥当な推論の代表例は三段論法だ。
大前提:人は死ぬ
小前提:ソクラテスは人間である
結 論:ゆえにソクラテスは死ぬ
これは論理的に妥当な推論3として認められる。
では以下の主張はどうだろうか。
大前提:すべての生物は繁殖する
小前提:人間は生物である
結 論:ゆえに人間も繁殖すべきである or 繁殖しない人間は間違っている。
これには明らかに論理の飛躍が見て取れる。すべての生物が繁殖するという事実がなぜ人間が繁殖すべき理由になるのだろうか。それならばすべての生物が共食いをしているとき、それを理由に人間も共食いをすべきなのだろうか?
このように、事実言明のみから当為言明を導くことはできない。これはヒュームが『人間本性論』において
私がこれまで出会ったいかなる道徳の体系においても、私はいつも以下のことに気が付いたものである。(中略)まったく突然、驚いたことに、「である」や「でない」といった通常の命題の繋辞ではなく、「べし」や「べきでない」と結びついた命題ばかり目にするのである。この変化は気づかないほど小さいが、しかし決定的な重要性を持つものである。
と記述したものである。確かに「このイチゴは甘くて美味しくて食べると幸せになる」という言明と「だからこのイチゴを食べるべきだ」という関係(繋辞)がどこにあるのだろうか?この鋭利な批判を加えたヒュームの名を冠して「ヒュームのギロチン」「ヒュームの法則」と呼ばれている。事実言明と道徳的言明の間をギロチンで断つ!もしくは事実言明から論理の飛躍をする人間の言葉を断つ!そんなイメージだろう。
これを認める以上、道徳的言明(記述的命題と対をなす規範的命題)はその正当化にほかの道徳的言明を持ち出してくる必要がある。
つまり人間が繁殖すべきだと自然を用いて主張したいのならば
大前提:生物は自然にかなった生き方をすべきだ
小前提:生物が繁殖することは自然にかなった生き方である
小前提:人間は生物である
結 論:人間は繁殖すべきだ
という結論が導かれるのである。もちろんこの大前提が正当化できるかどうかは別として、論理的に妥当な推論になっている。
まとめ
本章では三つの代表的な誤謬について見ていただいた。特にヒュームのギロチンは大変示唆に富んでいる。我々がこのギロチンから教訓を得るのならば、論理の飛躍や(隠れた、無意識な、しかし原理的な)当為言明に対して自覚的になるということだろう。私たちは無批判に 社会は存続されるべき、他者は尊重するべき という原理を内在化している可能性があるのだから。読者諸氏にはこのような誤謬でけむに巻かれることなく、もしくは自説を混乱させることなく、堂々とした倫理学の第一歩を歩みだしてほしいと思う。
読書案内
以下では規範倫理学で扱う倫理理論のうち功利主義を学ぶさいにオススメできる本を挙げている。功利主義者である筆者の知見の偏りに負っているため、倫理学入門に最適などと騙るつもりは一切ない。
児玉聡 『功利主義入門』 (ちくま新書,2012)
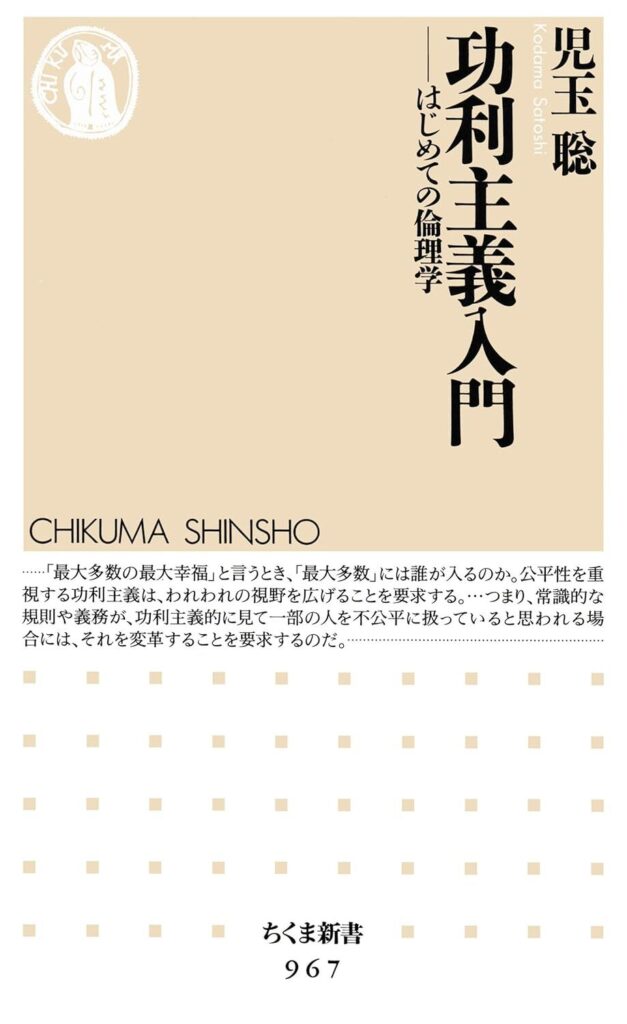
功利主義入門が筆者の倫理学の門戸を叩くものであったとするならば、そのブックガイドは開いたあとの広がりを見せてくれるものであった。しかしブックガイドのp.210には児玉氏の
倫理学の入門書としては今日でも最初に読むべき本と言ってよい。間違って最初に本書を読んでしまった人は、ぜひ手にしてみていただきたい。
という付言とともに加藤尚武 『現代倫理学入門』 (講談社学術文庫.1997)が挙げられている。
児玉聡 『実践・倫理学』 (勁草書房,2020)
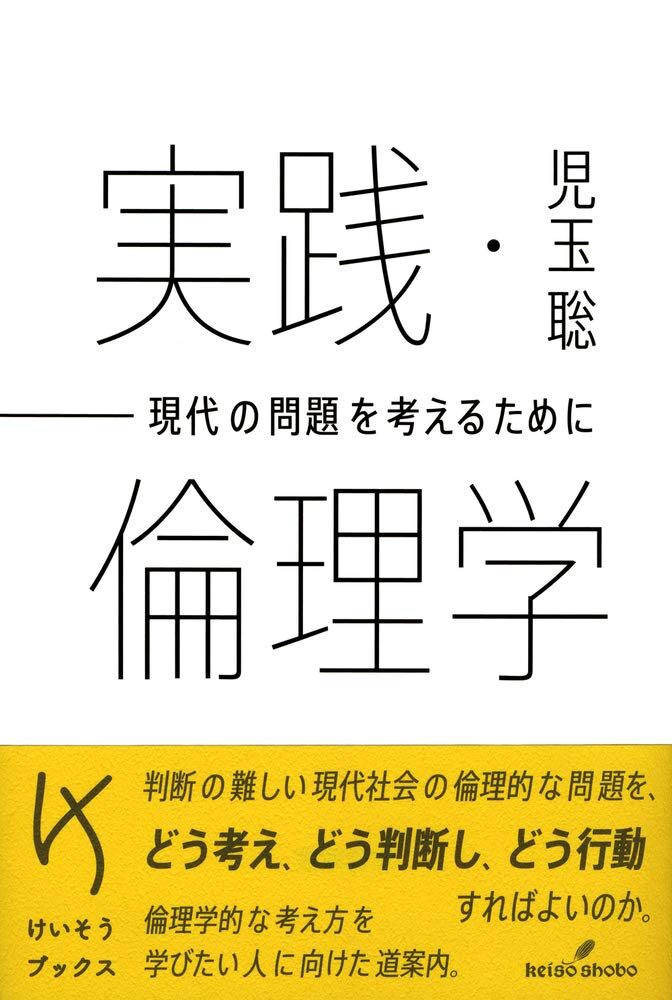
既に功利主義入門を、もしくはその他文庫本を読んで入門を終えているだろうか?それならば義務論や功利主義など特定の理論に立脚して現実の道徳的問題を考えてみよう。死刑制度に関する議論からはじまり自殺や安楽死、喫煙の自由などの問題に立ち向かう。
ピーター・シンガー(Singer,Peter) 『実践の倫理 新版』 山内友三郎,塚崎智訳, (昭和堂,1999)
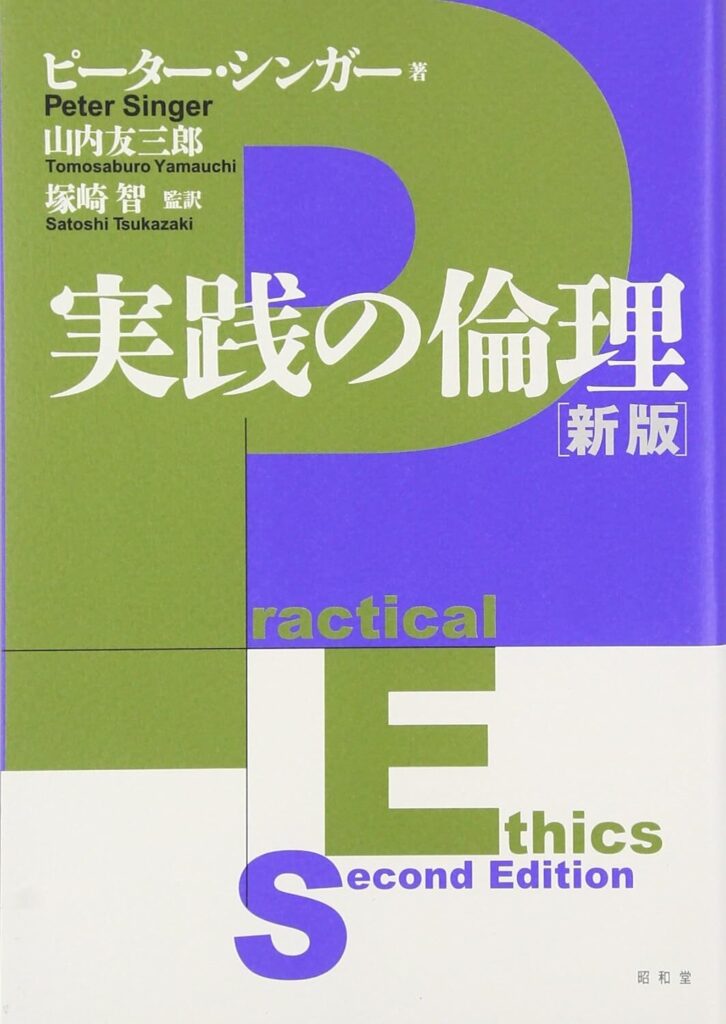
古く電子版もない本ではあるものの、一読の価値がある。道徳的であるとはどのようなことか、功利主義の正当化である1,2章からはじまり、Singerの代表的な主張である 動物の解放・中絶・安楽死・援助義務論 などすべて網羅された1冊。功利主義入門でもありSinger入門にもなる。
参考文献
プラトン(Plato) 『ソクラテスの弁明 クリトン』 久保勉訳(岩波文庫,1964)
スコット・ジェイムズ(Scott M.James) 『進化倫理学入門』 児玉聡訳(名古屋大学出版会,2018)
投稿者プロフィール

- 学際系の大学1年生
リベラルな功利主義、道徳実在論、反出生主義を勉強しています。noteではもう少しポエティックなことを言おうとしています。
SNS
・X(旧twitter)
・note
最新の投稿