令和の今日、日本中に「私を見て!」「俺を見ろ!」というメッセージの嵐が吹き荒れています。これを読んでいる人の中にも、自撮り写真や、華やかな食事の写真に気の利いたテキストを添えて、SNSに投稿した経験がある人も多いのではないでしょうか?
ここで質問です。あなたがそのキラキラした投稿をしたとき、胸にちょっとだけモヤっとするものを感じませんでしたか?
もしくは「もし、その投稿を毎日何回も続けたら私は病んでしまう」と感じたことはありませんか?
話はがらりと変わって、今度は日本文学についての質問です。明治の「小説家」といったらどんな姿をイメージしますか?
おそらく、締め切りに追われて、神経質に原稿用紙と頭をかきむしっているイメージではないでしょうか? 神経衰弱や胃潰瘍に悩まされ、「追い詰められた獣のような」不安を感じたと書いている夏目漱石や、どこまで史実かは怪しいものの、父から「くたばってしまえ」と勘当されたことをペンネームにしたといわれる二葉亭四迷、生涯に50回以上引っ越ししたといわれる国木田独歩などなど。個人差はあるでしょうが、小説家はみんな何だか変わっていて、苦しそう・・・。それは多くの人が共通して持っているイメージかと思います。
だいぶ離れた二種類の質問をしましたが、これには理由があります。
それは、「令和の映える『私』たちと、明治時代に『小説を日本に輸入』した明治の文豪たちが感じた苦しみは、実は似た性質のものだったのではないか?」と私は感じているからです。
キーワードは『私(わたくし)』を自ら語ること。『私(わたくし)』を自ら語ることよって初めて立ち現れる、出現する世界と言っても良いでしょう。
「語ることで初めて立ち現れる、出現する世界? いや、私は今存在している私の自撮り写真を投稿しているだけだけど・・・?」などと思った人も多いはず。
でも、それって本当ですか? 本当に事実を切り取って投稿しているだけなのなら、報告書を提出するのと変わりません。それなのに、なぜモヤっとしたり、SNS中毒になって病んでも投稿を辞められない人たちが後を絶たないのでしょう?
もちろん「いいね」が付くと嬉しい、承認された気になる、付かなければ病む、といったことはあるでしょう。明治の文豪たちも、自分が書いた小説が売れれば、嬉しかったはずです。これも確かに理由のひとつですが、私はこれは表面的な理由であると考えています。
儲かったり、承認されたりすれば『私』たちは嬉しい。だからもっと書く、投稿する。この意味では、小説とSNSは、よく似たシステムです。そしてこのシステムは、現代社会において基本的なOS=資本制社会でもあります。
ちょっとだけ、「モヤっと」「苦しみ」の正体=『私(わたくし)を自ら語ることで立ち現れる世界』に近づいてきました。
「SNSにキラキラした『私』やテキストを投稿するとなぜモヤっとするのか?」「SNS中毒になって病んでも、なぜ投稿を辞められないのか?」この問いの手がかりは、日本に「文学」が生まれた明治時代にありそうです。
なぜならば、令和のSNSの「モヤッと」「苦しみ」は、いにしえの小説家たちが感じた「苦しみ」にちょっと似ていて、その「苦しみ」が日本で最初に生まれ、「文学」が日本に生まれたのが明治時代だから。何事も、まっさらなところから何かが生まれる瞬間は、非常に分かりやすいものです。そして、ゼロから「文学」を立ち上げるということは、日本語にとって、ゼロから「世界」と『私(わたくし)』を立ち上げるということだったからです。そこに、令和の「モヤっと」「苦しみ」の正体のヒントがあります。
ではさっそく、日本に「文学」が生まれた明治を知るために、『日本近代文学の起源/柄谷行人』を読んでいきましょう。今回は、『第一章/風景の発見』『第二章/内面の発見』を解説していきます。
「風景の発見」という、忘却された転倒
今日、私たちは、人間は身体の表面で外界と『内面』が別れていて、外界のあなたと私の間には『風景』があり、私とあなたは断絶していて同じ『風景』を見ており、私の『内面』の言葉は『告白』がなければあなたには伝わらない、という世界観で生きています。これは、令和では当たり前のことすぎて、言葉にするとちょっと変な感じがするかもしれません。このような世界観から解脱して世界を観ることは、難しいと言って良いでしょう。
そして、今日の私たちは、当たり前のように皆同じ景色を見ている、皆同じ景色の中にいると思っています。これは、西欧の遠近法における位置に基づいているものの見方です。柄谷行人は宇佐美圭司の『比較』を引用しながらこう言っています。
遠近法における位置とは、固定的な視点を持つ一人の人間から、統一的に把握される。ある瞬間にその視点に対応する総てのものは、座標の網の目にのって相互関係が客観的に決定される。我々の現在の視覚も又、この遠近法的な対象把握を無言のうちにおこなっている。
日本近代文学の起源/柄谷行人(講談社文芸文庫) p22
ですが、柄谷行人はこうも言っています。
風景とは、一つの認識的な布置であり、いったんそれができあがるやいなや、その起源も隠蔽されてしまう。
日本近代文学の起源/柄谷行人(講談社文芸文庫) p24
そう、私たちが当たり前のものとして認識している『風景』は普遍のものではないというのです。
私の考えでは、「風景」が日本で見いだされたのは明治二十年代である。むろん見いだされるまでもなく、風景はあったというべきかもしれない。しかし、風景としての風景はそれ以前には存在しなかったのであり、そう考えるときにのみ、「風景の発見」がいかに重層的な意味をはらむのかをみることができるのである。
日本近代文学の起源/柄谷行人(講談社文芸文庫) p20
では、『風景』が見いだされた明治二十年代に、日本文学には一体何があったのでしょうか?
柄谷は、『風景の発見』の典型的な例として、国木田独歩の『忘れえぬ人々』を挙げています。作中、主人公である小説家の大津は、多摩川沿いの宿でたまたま知り合った秋山という人物に「忘れえぬ人々」(=忘れられない人々)について語る。ここでいう「忘れえぬ人々」とは、普通なら忘れてしまってもかまわないが、忘れられない人々のこと。親友や世話になった師は「忘れて叶ふまじき人」であり、「忘れえぬ人々」ではないと大津は語ります。
「忘れえぬ人々」の作中には、さまざまな人々が登場します。彼らは、主人公・大津の目に写った『風景』の中の人々として登場します。そのことは必ずしも奇怪なことではありませんが、作中、最後の数行でその奇怪さは表出します。
主人公・大津は自分の旅を振り返り、小説に記します。そして多摩川の宿屋でたまたま一緒になった男と「忘れえぬ人々」について語る様子を描くのですが、そこにいるのは「亀屋の主人」で、秋山ではありませんでした。大津は実際に登場し、語り合った秋山のことを忘れてしまったのです。
つまり、『忘れえぬ人々』という作品から感じられるのは、たんなる風景ではなく、なにか根本的な倒錯なのである。さらにいえば、「風景」こそこのような倒錯において見いだされるということである。すでにいったように、風景はたんに外にあるのではない。風景が出現するためにはいわば知覚の様態が変わらなければならないのであり、そのためには、ある逆転が必要なのだ。
(中略)ここには「風景」が孤独で内面的な状態と緊密に結びついていることがよく示されている。この人物(主人公)は、どうでも良いような他人に対して「我もなければ他もない」ような一体性を感じるが、眼の前にいる他者に対しては冷淡そのものである。いいかえれば、周囲の外的なものに無関心であるような「内的人間」inner manにおいて、はじめて風景がみいだされる。風景はむしろ「外」をみない人間によってみいだされたのである。
日本近代文学の起源/柄谷行人(講談社文芸文庫) p27
親友や師のことは忘れるはずもない。一方で取るに足りない、名前も知らないような他人に対して「我もなければ他もない」ような一体性を感じる。しかし、目の前にいる他者に対しては真の意味でどうでもよく、無関心で、忘れてしまう。そしてそれは孤独で内面的な状態と結びついている‐‐‐。そこには確かに倒錯があります。しかし、眼の前にいる他者のことは忘れてしまうのに、取るに足らない他者のことは慕情的な『風景』とともに「忘れえぬ」のは、なぜでしょう?
これは私の解釈ですが、それは、孤独で自意識が強い人間ほど、取るに足りない、名前も知らない他人に対してまで視線(自己)を拡張し、『風景の一部』としてしまうからではないでしょうか。そこにあるのは主体が中心であるという、やや自己愛的な倒錯です。一方で、別の自己を持っている他人には、主体の視線(自己)は拡張できません。つまり『風景』とは、西欧的な遠近法的なものの見方と、主体の自己の拡張があって成立するということです。
そしてもうひとつ、明治二十年代の『風景の発見』として、柄谷行人は正岡子規の写生文を挙げています。
彼は、ノートを持って野外に出、俳句という形で「写生」することを実行し提唱した。このとき、彼は俳句における伝統的な主題を捨てた。(中略)実は「写生」そのものに、独歩と同質のの転倒が潜在したことを見落としてはならない。(中略)「描写」とは、たんに外界を描くということとは異質ななにかだった。「外界」そのものが見出されねばならなかったからである。
日本近代文学の起源/柄谷行人(講談社文芸文庫) p30
正岡子規の「写生」は、従来の俳諧における「本歌取り」や「見立て」などの伝統的技法を離れ、「見たまま」を言葉により描写しようとしました。それは主体(見る人)と客体(見られるもの)の分離を意味し、主体と外界の分離を意味しました。
このように、日本文学において、主体と外界が分離し、主体から見た外界が『風景』となったのが最初に見られるのが明治二十年代です。これは、国木田独歩や正岡子規といった、最初期の作家たちが『風景描写』をおこなったとき、日本に『風景』は生まれたということです。そして、その小説や文学のフォーマットに沿って、後続の作家たちが『風景描写』を行ったことで、次第に日本人全体の主体と外界は分離し、誰もが『風景』の中にいる主体となりました。
令和の私たちが映える『風景』を写真に撮ってSNSに投稿するとき、それは遡れば、明治の文豪たちの思考をトレースしているのかもしれません。
そして、その『風景の発見』によって人間の外界と『内面』は別れることとなりました。令和の私たちが、風景以前の世界の配置はどうなっていたのか、もはや想像することは難しいでしょう。
風景がいったん成立すると、その起源は忘れさられる。それは、はじめから外的に存在する客観物のように見える。ところが、客観物(オブジェクト)なるものは、むしろ風景の中で成立したのである。主観あるいは自己(セルフ)もまた同様である。主観(主体)・客観(客体)という認識論的な場は、「風景」において成立したのである。つまりはじめからあるのではなく、「風景」のなかで派生してきたのだ。
日本近代文学の起源/柄谷行人(講談社文芸文庫) p42
章の冒頭文を繰り返しますが、今日、私たちは、人間は身体の表面で外界と『内面』が別れていて、外界のあなたと私の間には『風景』があり、私とあなたは断絶していて同じ『風景』を見ており、私の『内面』の言葉は『告白』がなければあなたには伝わらない、という世界観で生きています。
この私(主体)とあなた(客体)は、ひとつの『風景』の中にあって初めて存在することができます。『風景の発見』によって、『私(わたくし)』は見出された、と言えるでしょう。
この『風景』=外界が見出され、『内面』=私(わたくし)が見出されていく過程を柄谷行人はフロイトを引用しながら、こう言っています。
近代文学を扱う文学史家は、「近代的自己」なるものがただ頭の中で成立するかのような考え方をしている。しかし、すでに言ったように、自己(セルフ)が自己として存在し始めるには、もっと別の条件が必要なのだ。たとえば、フロイトは、ニーチェと同様に、「意識」を、はじめからあるのではなく「内面化」による派生物として見る姿勢をとっている。フロイトの考えでは、それまで内部も外界も無く、外界が内部の投射であった状態において、外傷(トローマ)をこうむりリビドーが内向化したとき、内面が内面として、外界が外界として存在しはじめる。ただし、フロイトはこう付け加えている。《抽象的言語がつくりあげられてはじめて、言語表象の感覚的残滓は内的事象と結びつくことになり、それによって内的事象そのものが、次第に知覚されるようになったのである》・・・(中略)しかし、フロイトの説においてもっとも重要なのは、「内部」(したがって外界としての外界)が存在し始めるのは、「抽象的思考言語がつくりあげられてはじめて」可能だといっていることである。われわれの文脈において「抽象的思考言語」とはなにか。おそらく「言文一致」だと言ってよい。
日本近代文学の起源/柄谷行人(講談社文芸文庫) p48
これをもう少し平易な言葉に言い換えてみましょう。『内面』も外界も無かった前近代的な人間が、トラウマになるようなストレスにさらされた時、外に向いていたエネルギーが内省的に内側に向かう。このとき『内面』が『内面』として、外界が外界として、存在するようになる。しかし、重要なのは、抽象的指向言語=具体的な感覚・経験を基盤とするが、それより広い意味を含み、より複雑な思考を可能とする言語が生まれたことによって、言語が言い表す人間の感覚は、人間の『内面』で起こっていることと結びつく。このことによって、人間の『内側』で起こっていることは知覚され、存在することになる。そして、この抽象的指向言語とは、日本人である私たちにとっての言文一致である。
これはつまり、私たちは、美しい景色や、心の感動を「風景描写」や「心理描写」をしていると思っていますが、実際には「描写」することで美しい景色や、心の感動は出現する、ということです。(そして、そのためには喋り言葉と書き言葉が一致し、心の中の抽象的な情緒を言葉にすることで『私』は『あなた』にそれを伝えることができる、という言文一致が必須なのですが、今回は主題から逸れるので省きます。)
これは同時に、現実と私の間の葛藤や、悲しみ、苦しみもまた、「描写」されることで出現したということです。0から1を生み出した、明治の文豪たちの苦しみは、想像を絶するものだったでしょう。
わかりやすい例として、日本人に医療用語としても一般用語としても定着している「肩こり」があります。「肩こり」と聞いて私たち日本人の多くは、明確な症状や原因を認知しており、予防治療法が文化的に確立されています。また夏目漱石が『門』で「肩こり」を近代人の神経症の症状として『描写』したこともあり、日本人の多くは「肩こり」を近代的な心身の不安や緊張と共に想起します。ですが、欧米の言語には完全に同じ意味を持つ言語は無く、欧米には「肩こり」は存在しません。シンプルに肩の痛みや張りとして認知・治療されるそうです。
タイトルの、「映える『私』を投稿すると、苦しくなるのはなぜだろう?」という問いのヒントがここにあります。令和の私たちは、私たちが既に存在していて、その姿を写真に撮ったり、感情をテキストにしてSNSに投稿していると思っています。ですがそれは、普遍的なものではありません。
私たちの『私(わたくし)』=自我は、私たちの自身の言葉によって「描写」されることによって生まれる、強化される側面があるということです。私達は自我や承認欲求が先にあって、映える『私』をSNSに投稿すると思っていますが、実際には私自身の言葉によって認識、「描写」されることによって自我は出現するのです。そしてそれは、自我の肥大化という危険と隣り合わせでもあります。もはや私たちはインターネットやSNSなしの生活は考えられませんが、もし「モヤっと」「苦しい」と感じたら、それは自我が肥大化しているサインかもしれません。
最後に、『日本近代文学の起源』の議論からは少し離れますが、このように日本に『私(わたくし)』や『風景』『内面』が発見されたのは何故でしょう?
それは、明治初期、ペルリの来航によって開国を迫られた日本は、急ぎ列強と張り合うため、近代国家になる必要があったからです。近代国家の基幹OSである資本制社会は、“原理的には”すべての人々が自由で平等な資格を与えられ、経済は人間の間の商品交換関係として処理される社会です。その前提となるのは、『私』『個人』の概念です。
そしてそれは、中央集権と完全に均質化した世界を目指し、小説が発明された明治では、新聞小説という当時の最新メディアや、学校教育をインフラとし、拡大しました。昭和、平成、令和の現在に至るまで、義務教育の国語の授業で必ず小説が取り上げられるのは、その名残です。
つまり、今日、日本語を解するほとんどの人が持っている『私(わたくし)』。これは、日本の近代化や資本制社会と密接な関係があるということです。
「後期資本主義」「脱成長」なんて言葉も出てきた昨今。150年の歴史ある「立身出世ナラティブ」にも、正直、私は食傷気味です。立身出世するために、現在世界中の人々が当たり前に持っている『私(わたくし)』が普遍的なものでは無いのなら、世界中の人々が『利他』に生きれば世界は平和になるのではないだろうか、と、雑然ながら私は思ったりするのでした。
参考文献
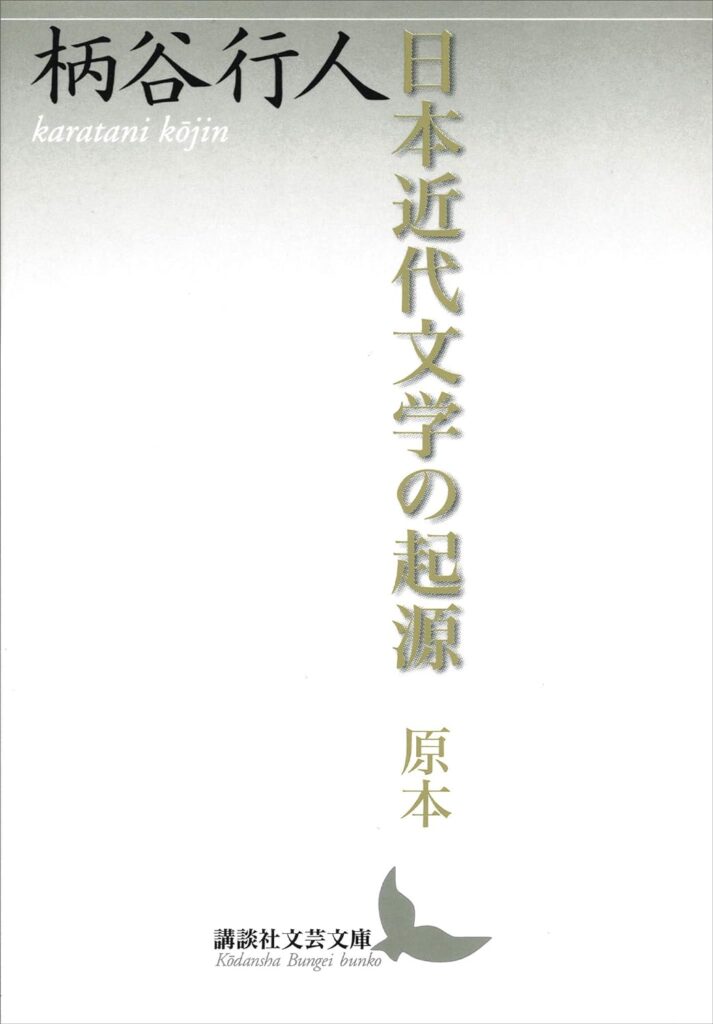
※参考にしたのは、日本近代文学の起源 (講談社文芸文庫 かB 1)だが絶版し、現在販売されているのは日本近代文学の起源 原本 (講談社文芸文庫 かB 8) なので注意(リンク、画像は原本版)
芥川賞はなぜ村上春樹に与えられなかったのか・擬態するニッポンの小説/市川真人(幻冬舎文庫)
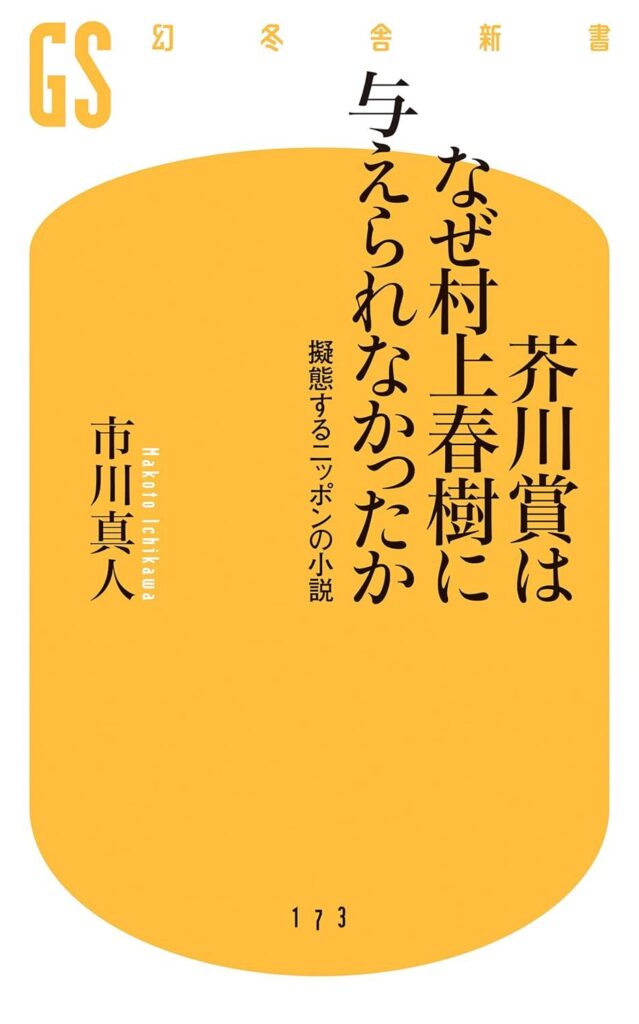
投稿者プロフィール

- 小説家・フリーライター。2025年は、日本各所に同時多発的に発足したポスト近代的なコミュニティをフィールドワークする予定。血縁に縛られず、共に暮す人を家族と思ってみる社会実験「拡張家族Cift」に参加中。好きな研究者は、柄谷行人、大塚英志、渡部直己、國分功一郎、河合隼雄などなど。
SNS
note
X
facebook



