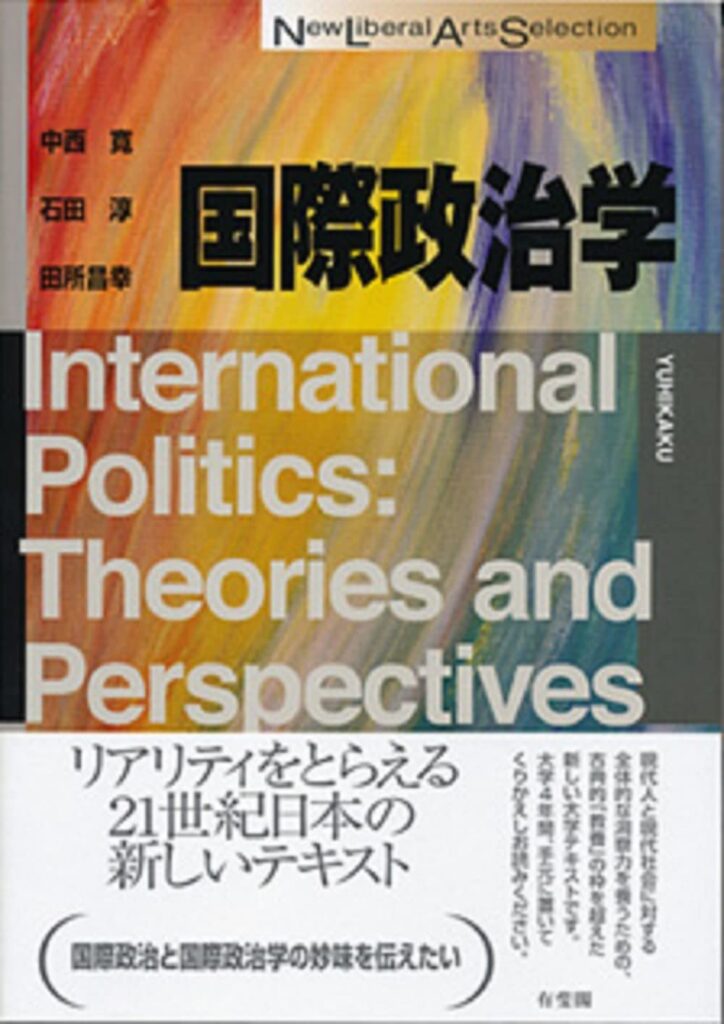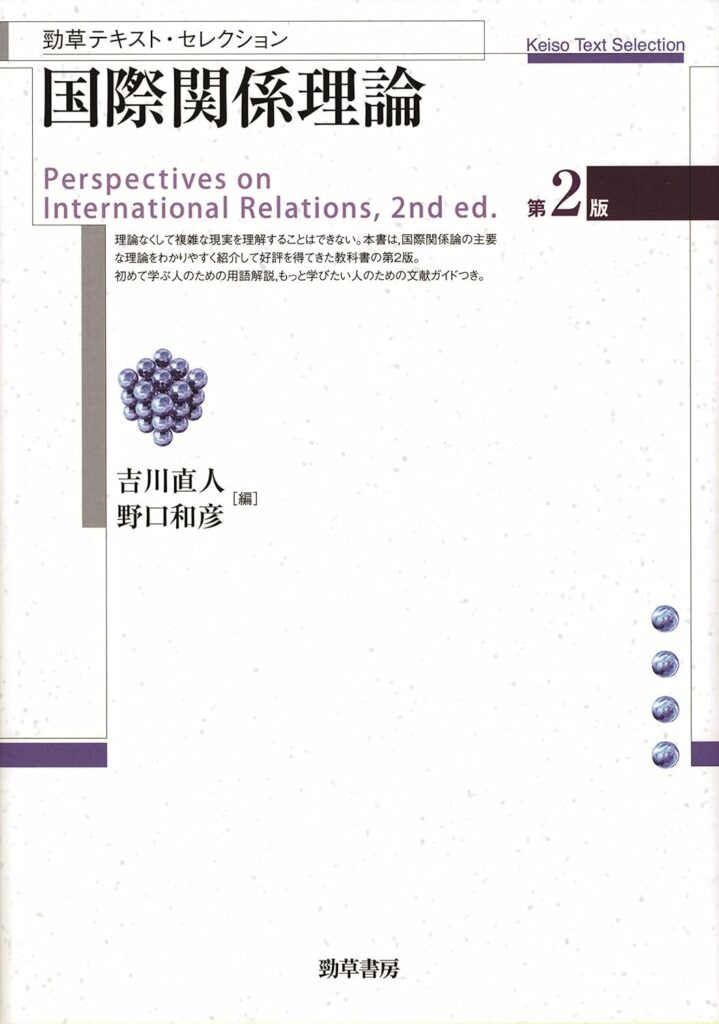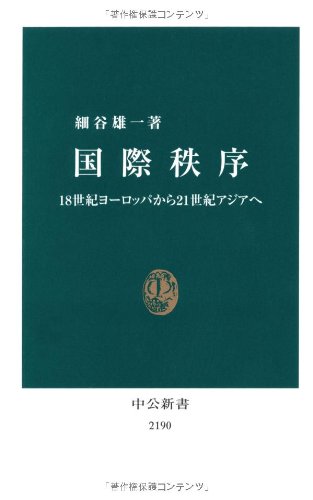3.0国際関係論の主要な理論
本章では、国際関係論でも特に主要な理論であるリアリズム・リベラリズム・コンストラクティビズムについて紹介します。そのとき、以下の要素にわけて説明します
・国際情勢を動かす要因は何か
・どういうときに国際情勢は安定するのか(具体例を含めて)
・批判や問題点
3.1リアリズム
3.1.1国際情勢を動かす要因は何か
リアリズムは、無政府的な国際システムにおいて国家がどのような動きをするのかを、パワー(軍事力や経済力などを含む国力)の視点から説明しようとする理論です。
リアリズムの論者たちが共有する前提は以下の通りです:
– 国際情勢は中央政府が存在しない無政府状態であること
– 国際関係における主要なアクター(行為主体)は国家であること
– 無政府世界において、国家の最優先目的は生存であること
– パワーは、この目的を達成するための重要かつ必要な手段であること
これらのことから、国際情勢において国家は自身の安全を確保するために行動する必要があり、その最も重要な要素はパワーである、リアリズムは考えます。
3.1.2どういうときに国際情勢は安定するのか
リアリズムにおいては国家間のパワーの釣り合いが取れているとき、国際情勢が安定します。
ただし、「どのような釣り合いが安定につながるか」については議論の余地があります。以下に、主な釣り合いのパターン(国際システム)を示します。
・多極システム:大国が3カ国以上存在する国際システム
・2極システム:大国が2つ存在する状態
・単極システム:大国が1カ国のみ存在する状況
ここで大国とは、「世界に影響力を行使できるだけのパワーをもつ国」という意味で捉えてください。
多極安定論は次のように考えます。大国の数が増えると国際関係が不確実になるため、国家指導者はより警戒的になり、軍事力の行使に慎重になります。また、大国の数が多いと臨機応変な同盟の組み替えが可能となります。これにより現状打破を目指す大国を効果的に牽制でき、結果として戦争が起こりにくくなるというのが多極安定論です。
この好例が19世紀後半ヨーロッパのビスマルク体制です。当時のヨーロッパの大国はイギリス・フランス・ドイツ・オーストリア・ロシアの5つでした。ビスマルクは当時のドイツの宰相です。
ビスマルクは隣国の大国のフランスからの侵攻を防止するため、複雑な同盟網を張り巡らせ、フランスを孤立させます。メジャーなところだけでも
・三帝同盟:ドイツ・オーストリア・ロシアの同盟
・三国同盟:ドイツ・オーストリア・イタリアの同盟
などを結びます。その結果、フランスの立場からすればドイツに侵攻すればドイツが率いる同盟群に対抗されてしまいます。他の大国もこの複雑な同盟網から抜け出すとフランスのように孤立するリスクを負うため、独立は困難です。このように、ビスマルク体制においては大国が複数存在したため多数の同盟が可能になり、それが国際システムの安定を支えていました。
2極安定論は次のように考えます。二極システムでは大国は1つの相手国のみを警戒すればよいため、パワーの大きさ、利益、同盟関係などの計算が容易になり、誤認が生じにくいです。戦争の原因の一つとして、「相手国は自分を攻めるつもりなのではないか」という疑心暗鬼があります。二極システムだと相手国の意図を読み取るのが多極システムよりも楽なので、2極システムが安定するという見方が二極安定論です。その好例が米ソ冷戦です。冷戦では大国の数が二国しかないため誤認が少なく、さらにイデオロギー上の対立から起こる争いを中東やアジアなどでの代理戦争に転嫁することで、国際情勢全体としては安定したのでした。
単極安定論では、大国とその他の国のパワーの差があまりにも大きいため、他国は大国に追随します。大国も現状変更よりも、単極システムの維持に利益を見出します。具体例としては、冷戦直後のアメリカが打ち出した新世界秩序と各国の追随です。
1990年8月に行われたイラクによるクウェート侵攻に対して、アメリカのブッシュ大統領(父)は、「新世界秩序」なる構想を打ち出し、国連決議にてイラク危機への対象を決定させました。つまり、ここで唯一の大国アメリカの圧倒的なパワーの指導のもと各大国が足並みをそろえることになったのです。
これまで見てきたように、リアリズムは国際システムの分析に関わります。つまり、サードイメージが分析対象です。
3.1.3批判や問題点
リアリズムになされる批判としては、「冷戦の終結を予測・説明できなかったこと」が挙げられます。
前節でみた通り、リアリズムの二極安定論の好例が冷戦なのです。だから、二極安定論からは冷戦の終結を説明することはできません。また、時系列的には冷戦のあとにブッシュ大統領(父)の「新世界秩序」が来ますが、リアリズムではシステムの移行についての理論化(たとえば二極から一極への移行)がなされていません。冷戦終結という世界史的に重要な出来事の説明がうまくできないことがリアリズムへの批判となっています。
3.2リベラリズム
3.2.1国際情勢を動かす要因は何か
リベラリズムは
・国家の内部性
・国際情勢における経済・政治的要素
を国際情勢を動かす(特に平和をもたらす)要素と考えます。
したがって、比較的セカンドイメージに重きを置いた理論であると言えます。
国家の内部性の重視について、リベラリズムは国家の内部の政治体制が国家の行動を決定する重要な要素であると考えられます。特に民主制の国家は協調的な政策を取り、戦争を避ける傾向が強いとされる一方、独裁制の国家は攻撃的であり、戦争を引き起こしやすいとみなされます。
パワーよりも政治・経済的要素の重視について、リベラリズムでは国家の行動が単なるパワーの利害計算によって決定されるのではなく、政治や経済といった要素によって左右されると考えられます。特に「善い国家」はパワーの追求ではなく、協調や経済発展を重視するため、国際政治において軍事力の重要性は相対的に低くなります。そのため、理想的な国際社会では国家間のパワーバランスはそれほど意味を持たず、協調的な関係が築かれるとされています。
以上のように、リベラリズムは国家の内部構造を重視し、政治・経済的要素をより重視するという特徴を持っています。
3.2.2どういうときに国際情勢は安定するのか
リベラリズムは以下の諸理論に分かれます。
・経済的相互依存論:国家が経済的に相互依存度を増すと互いに戦わなくなる
・民主主義の平和論:民主主義国家同士は戦争しない
・制度主義:国際制度機関が国際協調を推進し、大国の行動すら抑制する
経済的相互依存の立場からすれば、国際情勢の安定は、自由な経済交流を可能にするような秩序をつくることによって達成されることになります。というのも、このような国際秩序においては国家は経済的に繁栄しやすくなるからです。繁栄した国家は経済的に満足し、経済的に満足した国は自身に利益をもたらす国際秩序を壊す動機を持ちえません。
民主主義の平和論は主に2つの理由から説明されます。ひとつ目が「民主主義的価値観の共有」です。民主主義では人権の尊重が重視されます。だから、民主主義国の市民は他国の市民の人権を守ろうとするし、他国が自国の市民の人権を尊重するよう期待します。この価値観を共有しない非民主主義国はその限りではありませんが、民主主義国同士なら戦争はしない、というのが「民主主義的価値観の共有」からの説明です。
ふたつ目が「民主主義的制度による抑制」です。民主主義国においては、戦争のような重大な決定は議会を通す必要があり、また政府による情報統制も困難です。したがって、民主主義国において戦争に踏み切るには国民を説得する必要があり、さらにそれは困難です。このような制度を持たない非民主主義国は戦争に踏み切りやすいし、そのような国から侵攻された場合は民主主義国も防衛という形で戦争に関与せざるを得ません。しかしながら、制度上の制約が互いにある民主主義国同士なら戦争はしないだろう、というのが「民主主義的制度による抑制」です。
制度主義は、国家は国際制度機関の存在によって自己利益の計算をあきらめるようになり、これによって大国の利己的な行動は抑制され、協調が推進されるという考え方がされています。
たとえば、戦後すぐのアメリカは自国にとって自由貿易が有利になると考えてGATT(のちのWHO)を設立しました。自由貿易がアメリカにとって優位だった原因としてアメリカの圧倒的な生産力があります。しかし、これは70年代には既に崩れていた前提です。それにも関わらず国際社会は全体の利益になるのでGATTという機構を廃止せず、アメリカも自国の利益にならないという理由で廃止することはできませんでした。
3.2.3批判や問題点
リベラリズムへの批判としては、リアリズムと同じく冷戦終結の予測・説明ができなかったことにあります。冷戦終結は戦争の結果ではなく、アメリカとソ連のある種の「協調」によるものです。しかし、ソ連とアメリカに経済的相互依存は少なかったし、ソ連は民主主義だとは言えませんでしたし、さらにソ連とアメリカは異なる国際機構を率いていました。だから、リベラリズムの視点からはアメリカとソ連の協調を説明できないのです。
また、リベラリズムは国家以外のアクターの重要性をうたう論者もいるわりには、ここまで見てきたように国家中心の議論が多いです。これは批判というよりは今後の課題と言えるかもしれません。
3.3コンストラクティビズム
3.3.1国際情勢を動かす要因は何か
国際関係論におけるコンストラクティビズムは、国家が持つ理念に重きを置きます。理念とは、国家が所有している、国家自身のアイデンティティ、規範、規則などの間主観的な観念を指します。「間主観的(intersubjective)」とは、複数の主体の間で共有される意味や理解のことを指します。言い換えれば、個人の単なる主観(subjective)ではなく、かといって物理的な客観性(objective)を持つわけでもない、人々の間で成り立つ共通認識のことです。
その身近な具体例がお金です。お金自体は、紙や金属の物理的な物体にすぎません。しかし、人々が「この紙や金属には価値がある」という観念を共有することで、実際に商品やサービスと交換できるようになります。
このような間主観的な理念が、国家の利益が何かを決定し、ひいてはまた国家の行動を規定するというのが、コンストラクティビズムの考え方です。
3.3.2どういうときに国際情勢は安定するのか
前節の議論を受けて、「平和を愛する」という理念(国家アイデンティティや規範、規則)が多数の国家に共有されたときに、国際情勢は安定すると言えます。
たとえば、客観的にはすさまじい破壊力を持つ核ミサイルという武器でさえ、国家が持つアイデンティティや規範によってその意味が異なり、国家の行動を変化させます。
イギリスも北朝鮮も核ミサイルを保有しています。一方でイギリスが保有する核ミサイルの数はアメリカにとってほとんど問題になりません。これまでの歴史の積み重ねから、「イギリスはアメリカの友である」というアイデンティティが獲得されているからです。他方で、北朝鮮は中国・ロシアの支援を受けていることや、(日本にある)アメリカの軍事基地を脅かすような言動をしていることから、敵対国として認識されています。
しかしこのような国家が共有するアイデンティティは固定されたものではなく、歴史的な文脈のもとで変化していくものでもあります。冷戦においては、ソ連の国家アイデンティティは「共産主義の盟主でありアメリカの敵」というものでしたが、ゴルバチョフの登場により新しいアイデンティティを獲得します。ゴルバチョフはより自由主義的な国家を求め、ソ連およびロシア共和国のアイデンティティを変化させた結果、冷戦終結という国際協調に成功します。
コンストラクティビズムはこのようにアイデンティティや規範などの理念に注目することで、リアリズム・リベラリズムが成し遂げられなかった冷戦終結の説明に成功し、国際関係論の一大潮流になります。
国家が持つアイデンティティや規範に注目する点で、コンストラクティビズムはセカンドイメージを分析対象とします。しかしながら、ソ連のアイデンティティの変化にはゴルバチョフというリーダーが重要な役割を果たしたことから、ファーストイメージの分析も視野に入っています。
3.3.3批判や問題点
コンストラクティビズムへの批判としては、理念を分析の要にしているため、将来の予想は立てづらいことがあります。リアリズムやリベラリズムが主題としていた軍事力や経済力はある程度は予測が可能なものです。しかしながら、定量的ではない理念の変化は予測が困難です。
また、コンストラクティビズムの議論のある部分はリアリズムやリベラリズムで説明が可能であり、コンストラクティビズムの独自性が弱いのではないかという批判もあります。
4.0結び
これまで見たように、国際関係論は複雑な国際情勢から、パワーのバランスや経済的相互依存、理念など特定の要素を選択し、より簡素で明快な説明を行うための議論です。もちろん、各理論には批判もありますが、理論が議論のたたき台となることでより深く精緻な国際情勢の理解につながると考えられます。
最後に、国際関係論に入門するときに有用な本をいくつか紹介します。
中西寛, 石田淳, 田所昌幸.(2013).『国際政治学』有斐閣.
→理論の紹介はもちろんのこと、国際関係論の前史や今後の国際情勢への展望までおさめた射程の広い教科書です。
吉川直人, 野口和彦(編著). (2006).『国際関係理論』勁草書房.
→本記事で紹介した理論だけでなく、国際政治経済学や批判理論など、様々な理論を紹介してくれている教科書です。また、国際関係論の背景にある認識論の紹介もされています。
細谷雄一.(2012).『国際秩序 18世紀ヨーロッパから21世紀アジアへ』.中央公論新社
→近世ヨーロッパからオバマ大統領の登場までの世界史を、国際秩序を理解するための3つのモデルを用いて整理してくれています。
投稿者プロフィール

- プロフィール: 2025年4月から人文系の大学院生。学部時代は国際関係論を専攻。贈与経済に関心があり、柄谷行人『力と交様式』、近内悠太『世界は贈与でできている』、荒谷大輔『贈与経済2.0』などが愛読書。
X(旧twitter)